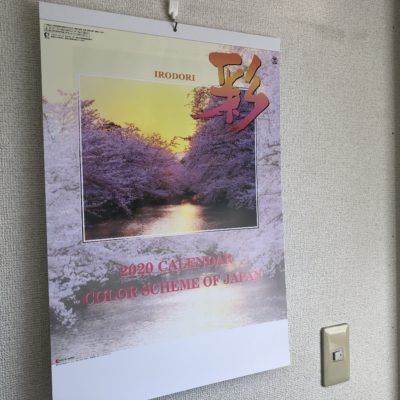声は五に過ぎざるも、五声(ごせい)の変は勝(あ)げて聴くべからず。色は五に過ぎざるも、|2月20日
Release: 2020/02/20 Update: 2020/03/01
声は五に過ぎざるも、五声(ごせい)の変は勝(あ)げて聴くべからず。色は五に過ぎざるも、
声不過五、五声之変不可勝聴也。色不過五、(五色之変不可勝観也。味不過五,五味之變不可勝嘗也。)
「音は宮(きゅう)・商(しょう)・角(かく)・徴(ち)・羽(う)の五つに過ぎないがこれを組み合わせると数えきれない変化が生まれ、残らず聞くことはとてもできない。色には青・赤・黄・白・黒の五つしかないが(これを組合わせると無数の変化が生じ、全部を見ることはてとてもできない。味には、辛(しん)・酸(さん)・鹹(かん)・甘(かん)・苦の五つしかないが、これを組合わせると無限の変化が生まれ、すべてを味わうことはとてもできない)」
五色(ごしき)の変は勝(あ)げて観るべからず。味は五に過ぎざるも、五味の変は勝(あ)げて嘗(な)むべからず。
2月20日、孫子・呉子一日一話(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
おはよございます。
たまりすぎたのでとりあえず更新です。
関連コンテンツ
彼を知り己を知れば、勝乃(すなわち)殆(あや)うからず。天を知り地を知れば、勝乃窮(きわ)まらず。(地形) 知彼知己、勝乃不殆。知天知地、勝乃不窮。 「敵と味方、双方の力を正確に把握し、天の時と地の利…
衆(しゅう)樹(じゅ)の動くは、来たるなり。衆草の障り多きは、疑わしむるなり。(行軍) 衆樹動者、来也。衆草多障者、疑也。 「木々がゆれ動いているのは、敵がやって来る証拠である。草むらに仕掛けがあるの…
其の戦いを用うるや、勝つも久しければ、則ち兵を鈍らせ鋭(えい)挫(くじ)く。(作戦) 其用戦也、勝久則鈍兵挫鋭。(攻城則力屈。久暴師則国用不足。) 「十万の大軍が敵と戦えば、たとえ勝つとしても、戦いを…
天とは、陰陽、寒暑、時制なり。地とは、遠近、険易、広狭、死生なり。(始計) 天者陰陽寒暑時制也。地者遠近険易広狭死生也。(将者智信仁勇厳也。法者曲制官道主用也。凡此五者将莫不聞。知之者勝、不知者不勝。…
軍行に険阻(けんそ)・潢井(こうせい)・葭葦(かい)・山林・蘙薈有らば、必ず謹んでこれを副索せよ。(行軍) 軍行有險阻潢井葭葦山林蘙薈者、必謹覆索之。(此伏姦之所處也。) 「行軍の途中に、①険阻な地形…