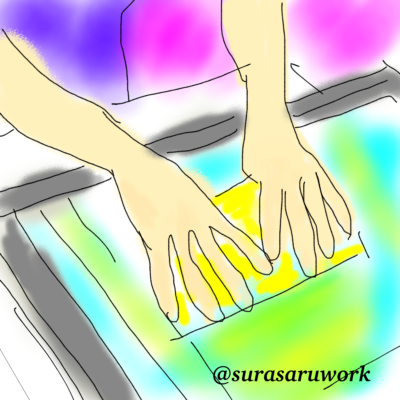人の地に入ること深くして、城邑(じょうゆう)を背(うしろ)にすること多きものを、重地と為す(九地)|6月22日
Release: 2020/06/22 Update: 2020/06/22
人の地に入ること深くして、城邑(じょうゆう)を背(うしろ)にすること多きものを、重地と為す(九地)
入人之地深、背城邑多者、為重地。
「敵の領内深く進攻し、敵の城や都市に囲まれて戦う場合、そのような地域を重地という」
このような地域で戦うと、兵糧や軍秣の補給がむずかしく、しかも敵の城や都市に囲まれているのでいつ攻撃されるかわからず、不安である。兵士たちは重苦しい心理状態にあるので、”重地”と定義したという(すこし、コジツケっぽいが)。
”人の地に入ること探し”によって、兵糧の補給が不自由になっているわけである。
6月22日、孫子・呉子一日一話(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
おはようございます。
敵の領内に深く入り込んで戦うイメージですね。
イチから知りたい!孫子の兵法には取るべき戦略で周辺地域から掠奪を行なうとあります。
こういう場所までは入って戦うためにはみやみに突っ込んではいけないのでしょうね。
自軍の兵の心理状況も重たくなるということですから。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
衢地(くち)には吾将に其の結びを固くせんとす。(九地) 衢地吾将固其結。 「交通の要衢の地である衢地においては、わたしは、友好国との親交を強化しなければならない」衢地とは、交通の要衢であるだけでなく、…
敵撃つべきを知り、吾が卒の以て撃つべきを知りて、(地形) 知敵之可撃、知吾卒之可以撃、(而不知地形之不可以戦、勝之半也。) 「敵に勝つ自信があり、味方は勝てるだけの実力を持っていると認識していたとして…
善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政(まつりごと)を為す。(軍形) 善用兵者、修道而保法。故能為勝敗之政。 「いくさ上手な者はよい政治を行ない、法令を整備し、これをきちんと守らせる…
兵は詐を以て立ち、利を以て動き、分合を以て変を為す者なり。(軍争) 兵以詐立、以利動、以分合爲變者也。 「作戦行動の基本は、敵をあざむくことである。有利な状況をつくりだして行動し、しかも、兵力を分散さ…
凡そ此の六者は、地の道なり。将の至任にして、察せざるばからざるなり。(地形) 凡此六者、地之道也。将之至任、不可不察也。 「以上のべた六項目(通、挂、支、隘、険、遠)が、地形に応じた戦い方の原則である…