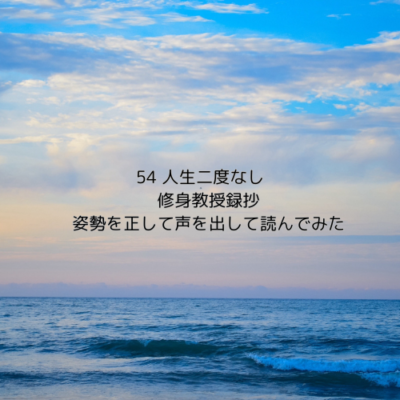人生の意義②力を出し切る
Release: 2022/08/02 Update: 2022/08/02
人生の意義②力を出し切る
自分が天からうけた力の一切を、生涯かけて出し切るところに、初めて、小は小なりに、大は大なりに、国家社会のお役にも立ち得るわけで、人生の意義といっても、結局はこの外にはないと言えましょう。【52】
「子曰く、吾れ十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲するところに従い矩を超えず。」
この学というのは単純な勉強ではなく、大学の道。修己治人の道。
こういう人物はどう育てれば育つのでしょうか。
幼い時から平々凡々なではない場合がほとんどですね。
人により幸せの定義は違いますが、常にこうやって自分と向き合う人物になれるというのは大事なことです。
自分を生かし切ってないです。
だんだんと体は衰えていきますから努力が必要になってきます。
様々な実践を試みるしかないですね。
関連コンテンツ
下座を行ずる② 世間がその人の真価を認めず、よってその位置がその人の真価よりはるかに低くても、それをもって、かえって自己を磨く最適の場所と心得て、不平不満の色を人に示さず、わが仕事に精進するのでありま…
一日の大安眠を得る途 一日の予定を完了しないで、明日に残して寝るというこおてゃ、畢竟人生の最後においても、多くの思いを残して死ぬということです。つまりそういうことを一生続けていたんでは、真の大往生はで…
そもそもこの世の中のことというものは、大抵のことは多少の例外があるものですが、この「人生二度なし」という真理のみ、古来只一つの例外すらないのです。しかしながら、この明白な事実に対して、諸君たちは、果た…
世間では、哲学者というものは、冷静でなくてはならぬと言われていますが、そしてそれにも一面の道理がないわけではありませんが、しかしこの言葉をもって、哲学者とは何ら情熱も感動もないもののように考えたら、…
世俗的な雑事の重圧を切り抜けられるかーそれは原則的には実に簡単明瞭であります。それは「すぐにその場で片づける」ということであり、「即刻、その場で処理して溜めておかない」ということこそ最上の秘訣であって…