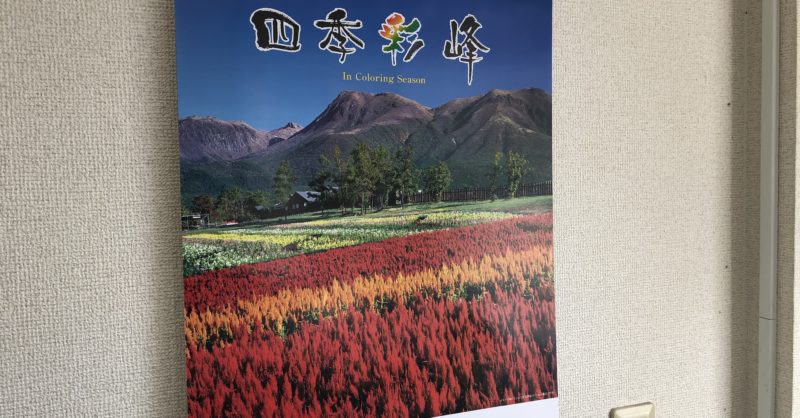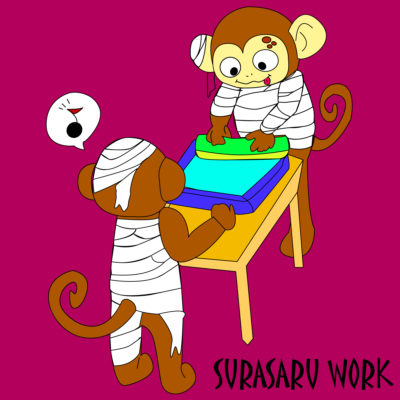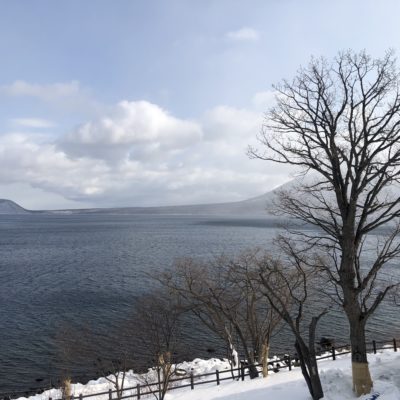卑してこれを驕(おご)らせ、佚(いつ)してこれを労し、親しみてこれを離し、其の無備を攻め、(始計)|1月9日
Release: 2020/01/09 Update: 2020/01/18
卑してこれを驕(おご)らせ、佚(いつ)してこれを労し、親しみてこれを離し、其の無備を攻め、(始計)
卑而驕之、佚而労之、親而離之、攻其無備、(出其不意、此兵家之勝、不可先伝也。)
「低姿勢にて出て油断させ、これらに休養充分にして敵を奔命(ほんめい)に疲れさせ、敵にくみする国と親交を結んで離間をはかり、こうして適の弱みにつけこんで、(その意表をつく。これこそが戦術上、勝利を収める秘訣であるが、その運用は状況に応じて変するものであり、あらかじめ固定しているのではない)」
”兵者詭道也”の具体的な戦術の後半である。
かっこ内は、其の不意に出(い)ず。此れ兵家(へいか)の勝にして、先に伝うべからざるなり。と訓ずる。
1月9日、孫子・呉子一日一話(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
関連コンテンツ
辞(ことば)卑(ひく)くして備えを益すは、進まんとするなり。辞強くして進駆(しんく)するは、退かんとするなり。(行軍) 辞卑而益備者、進也、辞強而進駆者、退也。 「敵の軍使が口ではへりくだったことをい…
凡そ此の六者は、敗の道なり。将の至任、察せざるべからざるなり。(地形) 凡此六者、敗之道也。将之至任、不可不察也。 「そもそも、以上のべたこの六項目(走、弛、陥、崩、乱、北)が敗北の常道であって、こう…
戦道必ず勝たば、主は戦う無かれと曰うとも、必ず戦いて可なり。(地形) 戦道必勝、主曰無戦、必勝可也。 「必ず勝つという見通しが立てば、たとえ主君が戦うなといっても、戦ってよい」これも前日の文章をふまえ…
其の途を迂して、これを誘うに利を以てし、人に後れて発し、人に先んじて至る。(軍争) 迂其途、而誘之以利、後人発、先人至。(此知迂直之計者也。) 「わざと回り道しながら、利でもって敵を誘惑し、敵より遅れ…
凡そ先に戦地に処りて敵を待つ者は、佚(いっ)し、後れて戦地に処りて戦いに趨(おもむ)く者は、労す。 凡先処戦地、而待敵者佚、後処戦地、而趨戦者労。(故善戦者、致人而不致於人。) 「そもそも、敵より先に…