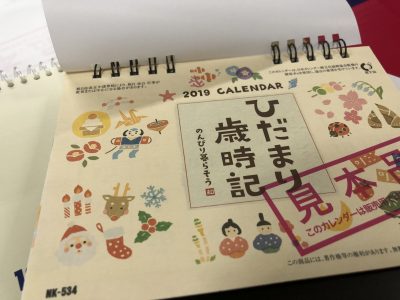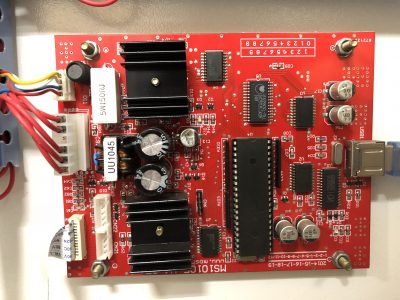君子―化・神|10月18日のことです。
Release: 2018/10/18 Update: 2018/10/18
君子―化・神
君子の過ぐる所のもは化し、存する所のものは神なり。(尽心上十三章)
すんしのすぐるところのものはかし、そんするところのものはしんなり。(じんしんかみじゅうさんしょう)
【訳】
心ある立派な人が通り過ぎると、人民は皆その徳に感化される。心ある立派な人が住むところは、その徳で人民は感化され、その様子はまるで神様のようだ。
[川口註ー原文とした『講孟箚記』(山口県教育会編『吉田松陰全集三』大和書房、昭和四十七年)において引用されている『集註孟子』には存する所のものは神とあるが、ここでは『神なり』とした。]
10月18日、孟子一日一言の言葉です。
徳のある人という視点でも人を見てみようと思いました。
普段の何気ないことからどう感じるかということが大事ですね。
自然と人が集まるようにするためには心をどのように保つかが大事ですね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
大 事ふること孰れか大なりと為す。親に事ふるを大なりと為す。守ること孰れか大なりと為す。身を守るを大なりと為す。(離婁上十九章) つかうることいずれかだいなりとなす。おやにことふるをだいなりとなす。ま…
聖人は百世の師なり 聖人は百世の師なり。(中略)而るを況や之れに親炙する者に於てをや。(尽心下十五章) せいじんはひゃくせいのしなり。(中略)しかるやいわにゃこれにしんしゃするものにおいてや。(じんし…
養ふ所以のものと知る 拱把の桐梓は人苟も之れを生(長)ぜんと欲すれば、皆之れを養ふ所以のものと知る。(告子上十三章) きょうはのどうしはひといやしくもこれをしょうぜんとほっすれば、みなこれをやしなうゆ…
一朝の患なきなり 自ら反して忠なり、其の横逆由ほ是くのごとくなれば、君子は曰はん、(中略)此れ亦妄人なるのみ、此くの如くんば則ち禽獣と奚ぞ撰ばん、禽獣に於て又何ぞ難ぜんと。是の故に君子は終身の憂ありて…
永く言に命を配し 永く言に命を配し、自ら多福を求む。(公孫丑上四章) ながくここにめいをはいし、みずからたふくをもとむ。(こうそんいかみよんしょう) 【訳】 末永く天命に従って誠実に人生を送り、自らの…