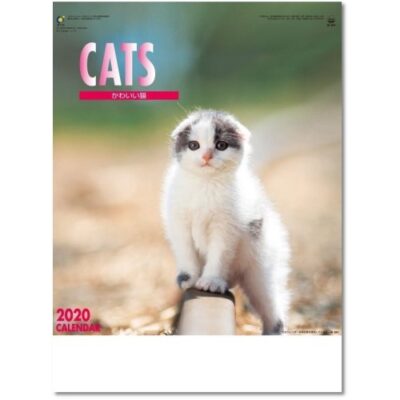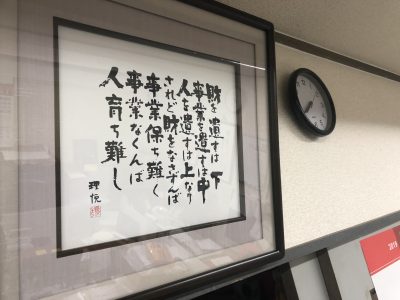命名の意義|7月16日のことです。
Release: 2018/07/16 Update: 2018/07/16
命名の意義
わが国では、昔から、造った品に名をつけていました。刀で申しますと、「菊一文字」とか、「浪切丸」とかいうのがあります。
人間の名づけは、元服の式、命名の式になります。一人前になったという印に、立派な人に名をつけて貰いました。これは、将来を祝福して、それを名に象徴して生命をふきこむのです。これが仏像なら、開眼供養の式で、開眼供養によって魂が入ることになるのと同じです。すべて、かくのごとく名をつけて、生き物としたのですが、これを祖先の行ってきた「式」というのであります。
7月16日、丸山敏雄一日一話幸せになるための366話、今日の言葉です。
名前を付けるというのは、それこそ大事なことなんでしょうね。
それによって魂を吹き込む。
物も呼び方呼び名があると愛着がわくものです。
人間につけるように物にも名をつける。
実際大事なことかもしれません。
パソコンにも名前をつけたり物もあの人と読んだりするのもいいかもしれませんね。
今日一日朗らかに安らかに喜んで進んで働きます。
関連コンテンツ
喜んで全力をつくす 心配しながら、結果を予想しながら、事に当る、こんな心持でした事は、必ず結果がよくない。 ただ喜んで全力をつくす。その時は予想もせぬよい結果が生まれる、幸福になる。 こうした心の持ち…
関西のある町に、銭湯を業としている方がありました。「どうしたならば、”日本一の気持ちのよいお風呂”と皆さん喜ばれるか」と心をくだいた結果、まず、一番に掃除をはじめました。 このほかに気をつけていること…
決死の覚悟 鉢巻は、いざという時、「我が身は神の占めるところとなれ。神様に差し上げるから、神よ、我が身を拠りどころ(依代)として乗り移れ」というような心持ちでしめたのである。決死の覚悟を決めたというし…
唯一不抜の存在 まことに、人の優越があるのではない、上下尊卑があるのではない。またその能力にも、技芸にも、甲乙があり品評されるようなものではない。 人がその正常心にあって、その全に生き、その満に働くと…
よろしく頼む 自転車も、乗りはじめに、馬にのるように「よろしく頼むぞ」といって乗ること、このとき人馬一体、という妙境が生まれてくるのです。 すべての機械・器具を、兄弟として扱うことが大切であります。…