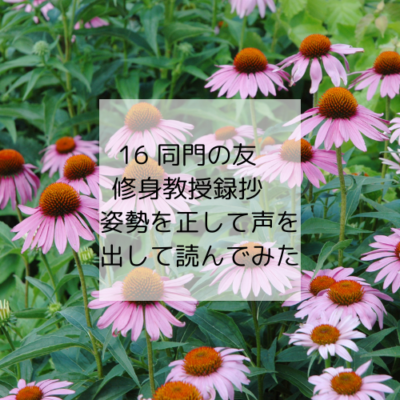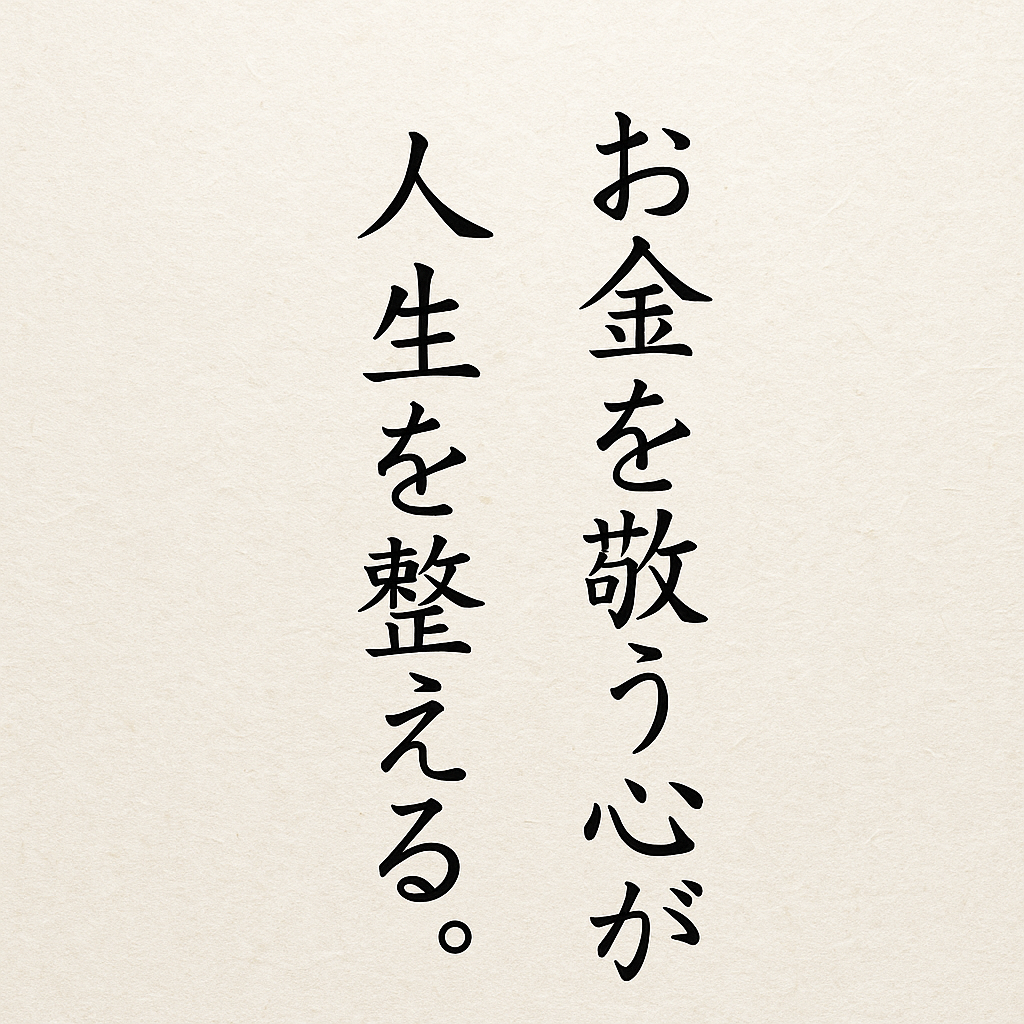後半生を何に捧げるか
Release: 2022/04/15 Update: 2022/04/15
後半生を何に捧げるか
人間は自分の後半生を、どこに向って捧ぐべきかという問題を、改めて深く考え直さねばならぬ。その意味において私は、もう一度深く先人の足跡に顧みて、その偉大な魂の前に首を垂れなければならぬ、と考えるようになった。【362】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
後半生になっていると実感はあるものの、今だまだまだ自分の一日をコントロールも出来ていない気が致します。
白髪が増え、生活習慣病なども医者に注意される有様ではどうにもならないわけですが自分の体に関しても気をつかっていかねばならぬとは実感するところですね。
さて、読書ということでさらには伝記を読めと教授はいうわけですが偉人の死にざまというものに着目していくことが必要な気がしますね。
どのように死ぬか。
自分が考える嫌な死に方は考えないうちにというのが嫌な気がします。
常に考えながら死にたい。
後悔でも感謝でもそういう頭が動く状態がいいと思うのです。
そのためにはいろいろと気を使わなければならないと実感します。
頭が元気でなければいけない。何を食べるか、どう運動するかも重要な気がします。
しっかりと考えて行動します。
関連コンテンツ
接する子どもの長所や美点を発見することの名人になること。叱るよりホメることに重点をおき、九つホメて一つ叱るぐらいでもなおホメ方が足りないということを心に銘記すべきだと思います。 #運命を創る100の金…
かの孔子が論語の始めに「朋遠方より来るあり、亦楽しからずや」と言っている朋というのは、実は「同門の友」ということであります。同時にそう考えますと、また格別の味わいがありましょう。すなわちただ遠方から友…
人生の出発点 「死生の問題」などと言いますと、諸君らのような若い人は、自分らのような若い者には、そんなことは縁遠いことだと思われるかも知れません。しかし私は必ずしもそうとは思わないのです。と申しますに…
金の苦労を知らない人は、その人柄がいかに良くても、どこか喰い足りぬところがある。人の苦しみの察しがつかぬからである 哲学者の森信三先生の語録に、「お金」に関するものが、意外に多いのにお気付きでしょう。…
古来独りを慎むということが大切とされていますが、慎独とは、ある意味では、この性欲を慎むところに、その最下の基盤があると言ってもよいでしょう。この問題はことがらの性質上、どうも正面から話を聞くという機会…