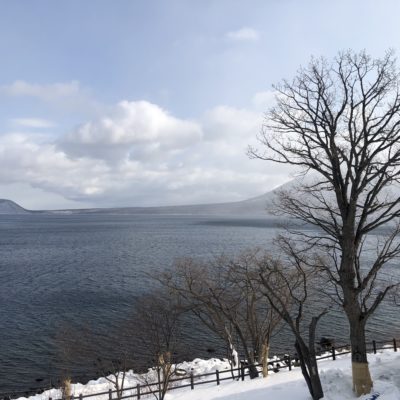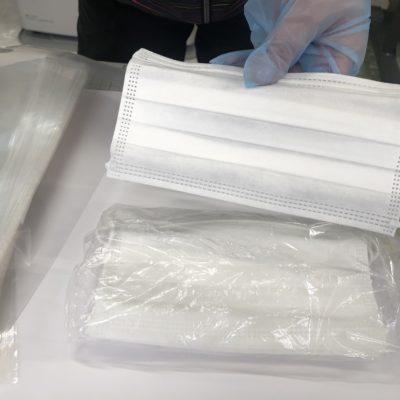是の故に、散地には則ち戦うこと無かれ。(九地)|6月26日
Release: 2020/06/26 Update: 2020/06/26
是の故に、散地には則ち戦うこと無かれ。(九地)
是故、散地則無戦。
「したがって、散地では戦いを避けるべきである」
戦場となる地域を、九つの種類にわけたので、以下でそれぞれの地域について、その特長や環境をとらえ、それに応じて指揮官のとるべき作戦を説明している。
”散地”とは、自分の領土内でいくさをするばあいである。
自国内で戦闘をすれば、勝っても負けても損害を受ける。したがって、戦わないのにこしたことはない。
6月26日、孫子・呉子一日一話(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
おはようございます。
自国内で戦わない。
自国内で戦わないようにするためにはどうすべきかですね。
攻めてきた場合はどうするか。
攻められないようにするにはどうするか。
常に考えていくことが大事です。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
凡そ先に戦地に処りて敵を待つ者は、佚(いっ)し、後れて戦地に処りて戦いに趨(おもむ)く者は、労す。 凡先処戦地、而待敵者佚、後処戦地、而趨戦者労。(故善戦者、致人而不致於人。) 「そもそも、敵より先に…
善く攻むる者は、敵其の守る所を知らず。善く守る者は、敵其の攻むる所を知らず。(虚実) 故善攻者,敵不知其所守;善守者,敵不知其所攻。(微乎微乎、至於無形、神乎神乎、至於無声、故能為敵之司命。) 「攻撃…
兵を形にする極(きょく)は、無形に至る。無形なれば、則ち深間(しんかん)も窺(うかが)うこと能わず、智者も謀ること能わず。(虚実) 形兵之極、至於無形。無形、則深間不能窺,智者不能謀。 「戦闘において…
算多きは勝ち、算少なきは勝たず。而るを況(いわ)んや算無きに於(おい)てをや。(始計) 多算勝、少算不勝。而況於無算乎。(吾以此観之、勝負見矣。) 「成算が多ければいくさに勝ち、少なければ負ける。まし…
彼を知り己を知れば、百戦して殆(あや)うからず。彼を知らずして己を知れば、一勝一負(いっしょういっぷ)す。(謀攻) 知彼知己者、百戦不殆、不知彼而知己、一勝一負。(不知彼不知己、毎戦必殆。) 「敵を知…