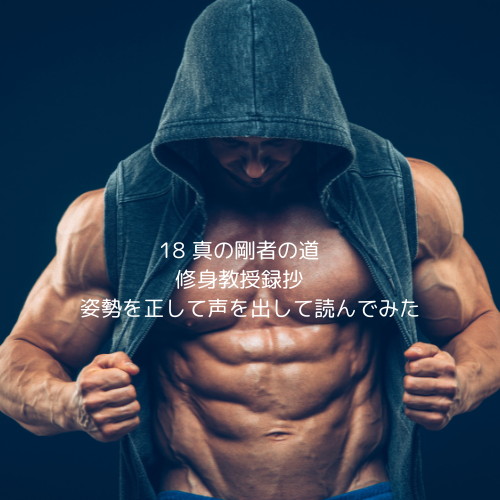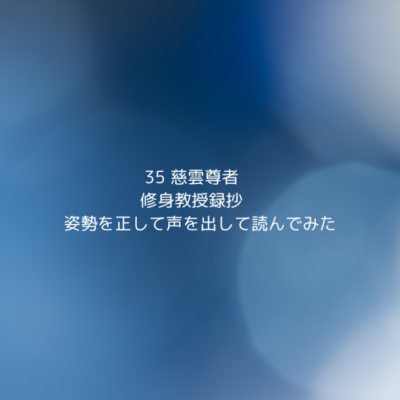18 真の剛者の道 修身教授録抄 姿勢を正して声を出して読んでみた
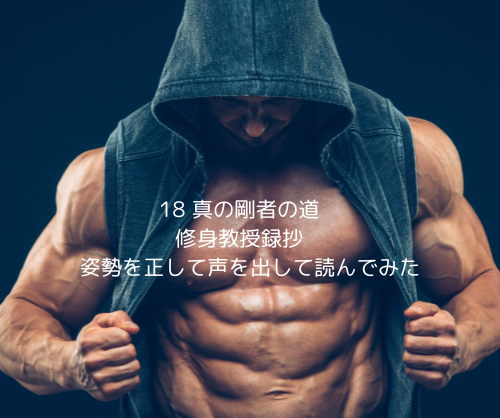
真の道徳修養というものは、意気地なしになるどころか、それとは正反対に、最もたくましい人間になることだと言ってよいでしょう。すなわちいかなる艱難辛苦に会おうとも、従容として人たる道を踏み外さないばかりか、この人生を、力強く生き抜いていけるような人間になることでしょう。その意味からは真の道徳修養は、またこれを剛者の道、否、最再剛者の道と言ってもよいでしょう。ですから、もしこの根本の一点をとり違えて道徳修養とは、要するに去勢させられた、お人好しの人間になることだなどと考えたら、そういった誤った修養なら、むしろ無いほうが遥かにましだとも言えましょう。
修身教授録
強い人間というのは、こういう人のことを言うのでしょうね。
大谷君は究極の剛者なのではないかと考えていました。
困難なことがありながらもあれだけ打つというのは並大抵のことではないですね。
いや、本当は奥様が剛者なのかもしれませんね。
多少なりとも剛者の道を歩む努力をしなければなりませんね。
いろいろ考えるところがあるのはいいことです。
準備をしっかりしてもいろいろと問題は発生するものです。
がんばりましょう。
本日の森信三一日一言は
世界史は表から見れば「神曲」の展開―そして之を裏返せば、人類の「業」の無限流転といえよう。
されば之に対して何人が、絶対的正邪善悪をいう資格があろう。
人間の業が地球をどうにかしているのは間違いないことかもしれませんね。
人間だけが住みやすい世界を作っています。
これは業というのは間違いないことですね。
何をすればいいのでしょうか。
尽きることのない業。
いずれ一旦リセットの時がくるのでしょうね。
本日の伝記は
津田 梅子 (つだ うめこ)
七歳で米国留学 【一八七一年、明治維新政府は欧米の先進文化に学ぶために、政府の中枢メンバーを欧米に派遣した。岩倉使節団と呼ばれた一行は、岩倉具視、大久保利通をはじめとする政府の要人が約二年間、欧米を視察して、新しい日本の国造りのモデルを探そうとした。実は、この使節団に五人の女性が加わっていた】
朝ドラで戦前の日本の法律で、女性のいろいろな不平等を感じていましたが当時は画期的な女性だったんでしょうね。
偉人は世界を経験してると感じます。
なかなか海外などに行く機会がないんですが、いろいろと考えないといけませんね。
いろいろな場所に行ってみるべきですね。
山田 寅次郎 (やまだ とらじろう)
日本とトルコの架け橋 【トルコは親日的だと言われている。山田寅次郎の存在がそれに一役かったことは、間違いない。彼は明治時代、二十年以上にわたってトルコに住み続けた稀有な日本人であった。日本とトルコが身近な国になるよう尽力した。まさに国際交流の先駆けであり、日本とトルコの架け橋であった】
トルコと日本が仲がいいというのは何となく聞いたことがありましたが、このような人がいたとは知りませんでした。
なかなか深堀していなと感じますね。
本日はここまでです。
ありがとうございます。