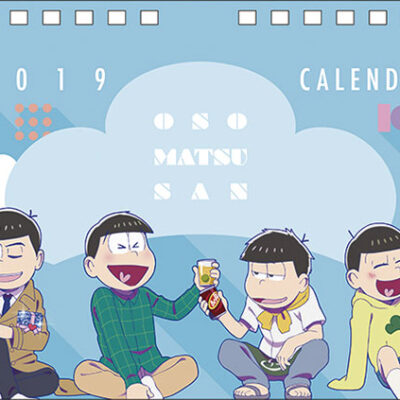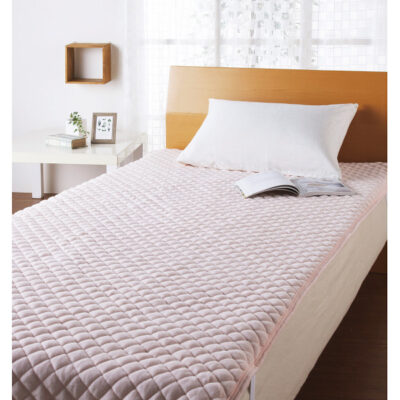夜以て日に継ぎ|6月5日のことです。
Release: 2018/06/05 Update: 2018/06/05
夜以て日に継ぎ
其の合わざるものあれば仰いで之れを思ひ夜以て日に継ぎ、幸いにして之れを得れば坐して以て旦を待つ。(離婁下二十章)
そのあわざるものあればあおいでこれをおもいよるもってひにつぎ、さいわいにしてこれをうればざしてもってあしたをまつ。(りろうしもにじゅうしょう)
【訳】
(周公は敬慕する禹、湯王、文王、武王が実践されたことで)当時の実情に合わないものがあると、天を仰いで思いを巡らせ、昼夜を徹して考え続けた。幸いに妙案が浮かぶと、すぐに実行したいと思い、床にもつかず、夜明けをまちこがれた。
〇松陰は、「我が国にも、古代中国のあり方をそのまま真似て、失敗するものが少なくない。周公のように実情に合うか否かを思索するべきである」と記している。
孟子一日一言、6月5日の言葉です。
論語も、孟子も全ての言葉は今の時代にも通じるものもありますが、解釈は今の時代に合わせなければいけませんね。
時代、時代で変わるということです。
道徳などもまさしくそうで国によっても時代によっても正しいことは変わっていきます。
それでも人は正しいことを考えなければいけませんね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
法を行ひて以て命を俟つ 君子は法を行ひて以て命を俟つのみ。(尽心下三十三章) くんしはほうをおこないてもってめいをまつのみ。(じんしんしもさんじゅうさんしょう) 12月20日、孟子一日一言の言葉です。…
天爵を修めて、人爵之れに従ふ① 天爵なるものあり、人爵なるものあり。仁義忠信、善を楽しみて倦まず、此れ天爵なり。公卿大夫、此れ人爵なり。(告子上十六章) てんしゃくなるものあり、じんしゃくなるものあり…
召さざる所の臣あり 召さざる所の臣あり。(公孫丑下二章) 【訳】 (これから大きな功業を成し遂げようとする君主には)決して呼びつけにはしない家臣がいる。 〇松陰は、「劉備には(家臣であっても、自分より…
己れを害するを悪みて 諸侯其の害するを悪みて、皆其の籍を去る。(万章下一章) しょこうそのがいするをにくみて、みなそのせきをさる。(ばんしょうしもいっしょう) 【訳】 (わがまま勝手なことをしていた)…
善教 善政は善教の民を得るに如かざるなり。(尽心上十四章) ぜんせいはぜんきょうのたみをうるにしかざるなり。(じんしんかみじゅうよんしょう) 【訳】 法度、禁令をきちんと整備した善政は、仁義道徳のよい…