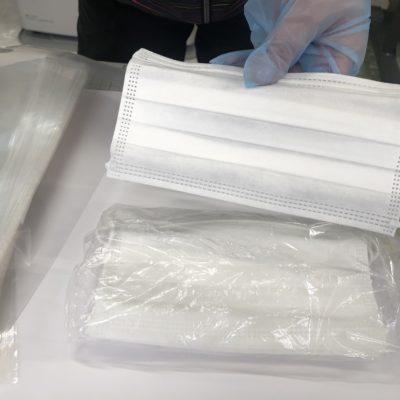師を囲めば必ず闕(か)く。 窮寇(きゅうこう)には迫ること勿れ。 此れ兵を用うるの法なり。(軍争)|4月4日
Release: 2020/04/04 Update: 2020/04/04
師を囲めば必ず闕(か)く。
窮寇(きゅうこう)には迫ること勿れ。
此れ兵を用うるの法なり。(軍争)
囲師必闕。窮寇勿迫。此用兵之法也。
「⑦敵の部隊を包囲した場合、必ずどこかに逃げ口を開けておくべきで、決して完全包囲してはならない。
⑧窮地におちいった敵を、追い詰めてはならない。
これが戦闘上の法則である」
以上が『孫子』の説く戦闘の八原則であるが、日本の兵法家には異なる意見も多いだろう。特に⑦の”囲師必闕”は、日本軍の”袋のねずみにする戦い方”とは著しく違っている。
4月4日、孫子・呉子一日一話(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
おはようございます。
追い詰めてしまったら敵が通常にはない力を発揮するということはありますね。
完全包囲して戦意を無くさせる場合もあるかもしれません。
情況をみて情報を入れて判断するべきことなんでしょうか。
難しいところです。
百戦百勝は善の善なるものあらず。
味方の被害を考えると孫子の方法がいいかもしれませんね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
故に、兵は拙速(せっそく)を聞くも、未だ巧(こう)の久しきを睹(み)ざるなり。(作戦) 故兵聞拙速、未睹巧之久也。(夫兵久而国利者、未之有也。) 「したがって、短期決戦に出て成功した例は聞いたことがあ…
以て往(ゆ)くべく、以て返り難きを挂と曰う。挂形は、敵に備え無ければ出でてこれに勝つ。 可以往。難以返曰挂。挂形者、敵無備出而勝之。(敵若有備出而不勝、難以返不利。) 「行くことはできるが、引き返すこ…
令発するの日、士卒の坐する者は涕襟(なみだえり)を霑(うるお)し、偃臥する者は涕巸(なみだおとがい)に交わる。 令発之日、士卒坐者涕霑襟、偃臥者涕交巸。(投之無所往者、諸劌之勇也。) 「いよいよ出陣の…
彼を知り己を知れば、百戦して殆(あや)うからず。彼を知らずして己を知れば、一勝一負(いっしょういっぷ)す。(謀攻) 知彼知己者、百戦不殆、不知彼而知己、一勝一負。(不知彼不知己、毎戦必殆。) 「敵を知…
軍政に曰く、言えども相聞こえず、故に金鼓(きんこ)を為(つく)る。視(しめ)せども相見えず、故に旌旗(せいき)を為ると。 軍政曰、言不相聞、故爲之金鼓。 視不相見、故爲之旌旗。 (夫金鼓旌旗者、所以一…