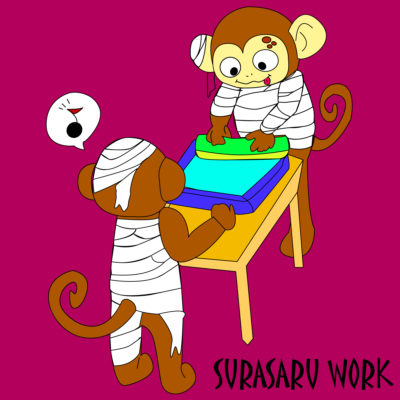夫れ地形は兵の助けなり。敵を料(はか)りて勝を制し、険阨遠近(けんあいえんきん)を計るは、上将の道なり。(地形)|6月4日
Release: 2020/06/04 Update: 2020/06/04
夫れ地形は兵の助けなり。敵を料(はか)りて勝を制し、険阨遠近(けんあいえんきん)を計るは、上将の道なり。(地形)
夫地形者兵之助也。料敵制勝、計険阨遠近、上将之道也。
「地形というものは戦闘上の有利な補助手段である。敵の動きを察知し、地形の険阻や遠近をにらみあわせながら作戦をたてるのはあ、将軍たちるものの務めである。」
”阨”はやくともよむ。ふさがっているという意味。ここでは、ジャングル、川、湖沼などで通路がふさがっていること。
”上将”は、春秋時代には上軍の将(当時は全軍を上・中・下軍にわけた)のことであるが、その後は将軍とか全軍の将をいうようになった。
6月4日、孫子・呉子一日一言(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
おはようございます。
地形は戦争に於ける補助的要因。
総リーダーたるもの地形(どこで戦うか)などを熟慮しなければいけない。
当然のことですね。
会社でいえば自社の強みを明確に知っていて今はどこで戦うべきかをわかっていることは大事です。
そういうことが明確でないから迷うこととなるんでしょうね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
其の途を迂して、これを誘うに利を以てし、人に後れて発し、人に先んじて至る。(軍争) 迂其途、而誘之以利、後人発、先人至。(此知迂直之計者也。) 「わざと回り道しながら、利でもって敵を誘惑し、敵より遅れ…
衢地(くち)には吾将に其の結びを固くせんとす。(九地) 衢地吾将固其結。 「交通の要衢の地である衢地においては、わたしは、友好国との親交を強化しなければならない」衢地とは、交通の要衢であるだけでなく、…
将、九変の利に通ずる者は、兵を用うることを知る。将、九変の利に通ぜざる者は、 将通於九変之里者、知用兵矣。将不通於九変之利者、(雖知地形、不能得地之利矣。治兵不知九変之術、雖知五利、不能得人之用矣。)…
将、九変の利に通ずる者は、兵を用うることを知る。将、九変の利に通ぜざる者は、(九変) 将通於九鍵之利者、知用兵矢、将不通於九鍵之利者、(難知地形、不能得地之利参、治兵不知九鍵之術、難知五利、不能得人之…
治を以て乱を待ち、静を以て譁(か)を待つ。此れ心を治むる者なり。近きを以て遠きを待ち、(軍争) 以治待乱、以静待譁。此治心者也。以近待遠、(以佚待労、以飽待飢、此治力者也。) 3月30日、商いの心一日…