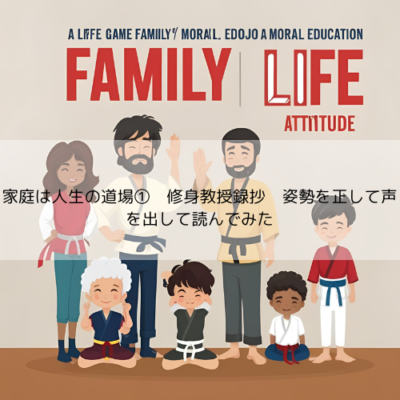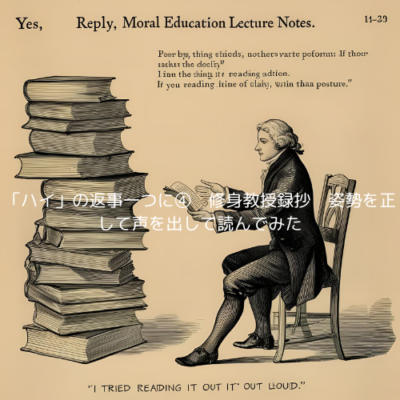出処進退でわかる人の真価
Release: 2022/07/19 Update: 2022/07/19
出処進退でわかる人の真価
すべて物事は、平生無事の際には、ホンモノとニセモノも、偉いのも偉くないのも、さほど際立って分からぬものです。ちょうどそれは、安普請の借家も本づくりの住居も、平生はそれほど違うとも見えませんが、ひとたび地震が揺れるとか、あるいは大風でも吹いたが最期、そこに歴然として、よきはよく悪しきはあしく、それぞれの正味が現れるのです。同様にわれわれ人間も、平生それほど違うと思われなくても、いざ出処進退の問題となると、平生見えなかったその人の真価が、まったくむき出しになってくるのです。【430】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
常、日ごろの行いが大事ということですね。
人に見られている時だけとか、何か理由があって行う行為はホンモノにならないというのはそうでしょう。
「説法100日、屁一つ」ということわざは知りませんでした。
日々の積み重ねも引き際の悪さで台なしになるという場合はあるかもしれません。
引き際を見苦しくなく過ごすためには常に実践することが大事です。
勇気が必要だと感じました。
関連コンテンツ
家庭生活こそは、実に人間修養の根本道場というべきでしょう。特に女性は、その生活の「場」がほとんど家庭といってよいわけですから、女性にとっては家庭は唯一の修養道場といってよいでしょう。もちろん男性にと…
昔の婦人は、「寝顔は夫に見せぬ」ということが、妻としての大切なたしなみの一つであったといわれていますが、現在こうしたたしなみを失わない女人が、果たしてどの程度にあると言えるでしょうか。なるほどどの家…
人生二度なし 諸君!この人生は二度とないのです。いかに泣いてもわめいても、そのわれわれの肉体が一たび壊滅したならば、二度とこれを取り返すことはできないのです。したがってこの肉体の生きている間に、不滅な…
ヒントは書物の中に 諸君が将来何らかの事に当たって、必要が生じた場合、少なくともそれを処理する立場は、自分がかつて読んだ書物の中に、その示唆の求められる場合が少なくないでしょう。つまりかつての日、内心…
楽天知命 いやしくもわが身の上に起こる事柄は、そのすべてが、この私にとって絶対必然であると共に、最善なはずだ。 それ故われわれは、それに対して一切を拒まず、一切を受け入れて、そこに隠されている神の意志…