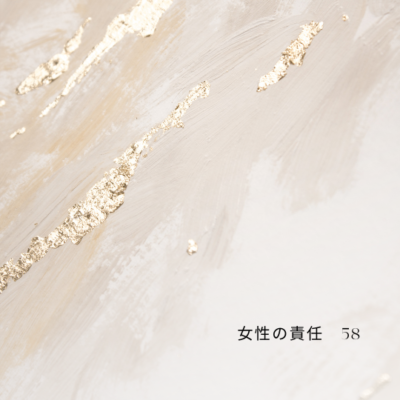対話の心得
Release: 2022/10/13 Update: 2022/10/13
対話の心得
対話の際の心得ですが、それには、なるべく相手の人に話さすようにする。さらに進んで相手の話を聞こうとする態度が、対話の心がけの根本と言ってもよいでしょう。
つまり、なるべく聞き役に回るというとです。もちろん、全然喋らないというのも面白くありませんが、しかし自分は主として聞き役に回って、対話としては上乗なるものでしょう。【198】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
傾聴することは大切ですが、適度な相槌や会話の流れをみて自分の言葉を適度に入れることは大切なことです。
会話というものが一番のコミュニケーションなんですからどう考えて話をするかです。
思いやりと言ってもいいかもしれません。
コーチングという会話のテクニックもあるくらいですから。
しかし、先生はどんな些細なことも真剣だったんでしょうね。
寿しの食べ方、ビールの次ぎ方など様々なことについての話があります。
真剣に生きるというのは細かなことを自分自身でどう感じ実践するのか。
まだまだ爪の垢まで理解していないと思います。
関連コンテンツ
今かりに人生を山登りに喩えますと、四十歳はちょうど山の頂のようなもので、山の頂に立って見ますと、わが来し方も、初めてしみじみと振り返って見ることができると共に、また後半生をいかに生きたらよいかというこ…
「整頓」ということは、ある意味では主婦としての最大の徳といえるかも知れません。実際整頓の不得意なひとを貰ったご主人は、生涯うだつが上がらんとも言えましょう。 それと申すのも、その家の家風というも…
信とは 「信」とはこの天地人生の真実を、一々中身のせんぎ立てをしないで丸受け取りに受け取ることです。すなわちまた、この天地人生の実相をつかんだ人の言葉を、素直に受け入れるということです。【271】 #…
女性の弛緩は民族の弛緩となり、女性の変質は民族の変質につながります。民族の将来は女性のあり方如何によって決まると言っても決して過言ではないわけです。 #運命を創る100の金言 #森信三 時…
「報徳記」と「夜話」に学ぶ 極端に言えば、小中学校では尊徳翁の「報徳記」と「夜話」とを読ませれば、修身書はいらぬとも言えるほどです。教科書を躬をもって突き抜けていくだけの信念がなくては、何を言っても無…