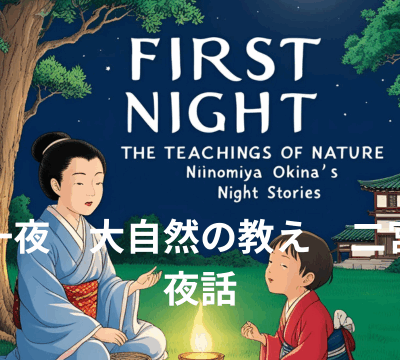第五夜 天道は自然のままだが、人道は手を加える

今夜は冬至だ。夜は長いがこれは天命なんだ。夜の長いのを嫌って短くしようとしてもそれはどうすることもできない。こういうのを天道というんだな。
さてこの行灯の皿に油がいっぱいある。これも天命なんだ。この一皿の油でこの長い夜をひと晩じゅう照らすには十分ではないが、これまたどうしようもないことだな。ともに天命なんだが、もし人が燈心を細くすれば、夜中に消えるはずの灯火も明け方まで持たせることができる。ここが人道を尽くさねばならぬという理由なんだ。
たとえば伊勢詣をする人が、江戸から伊勢まで百里だとして旅費が十円ならば、上り下り二十日として一日五十銭にあたる。これは天命だ。それを一日六十銭ずる使えば二円不足し、四十銭ずつ使えば二円余ることになる。
このことは人事によって天命を伸ばしたり縮めたりすることができるということのたとえなんだな。この世は自転運動の世界だから決して止まっているということはない。人が勤めたり、怠けたりすることで天命も伸ばしたり縮めたりすることができるんだ。
たとえば、今朝使う薪がないということは一応天命だが、それも明朝とってくればあるんだ。いま水桶に水がないということは差しあたり天命だが、汲んでくればあるということになる。つまりこのように人事を天命に加えることにより、人間に都合のよういほうへ変えていくことができるのであって、万事みなこの道理のとおりなんだよ。(二九)
なんでも、物事にはどおりというものがありますが、まさしくそのことを説いているように感じます。
人間は天命というものに従いながらもより良くする方法を考える頭がある。
しかしながらそのことも人によって捉えることが違いますね。
天命と人事──ある静かな夜に思うこと
『二宮翁夜話』の中で、「天命」と「人事」の関係について語られる一節を読み返して、しみじみと考えさせられました。
たとえば、夜の長さは人間にはどうすることもできない。それは「天道」であり、自然の摂理そのものです。でも、灯火の油が限られている中で、芯を細くすれば夜明けまで持たせることができる──ここに「人事を尽くす」意義があるのだと翁は説きます。
これはまさしく、物事には「道理」があるということの証であり、人間が本来持っている知恵と判断力の話です。
経営の現場でも、「景気が悪い」「コストが上がる」「人が辞める」といった避けがたい“天命”に直面することがあります。しかし、その中で何を残し、何を削り、どこに力を入れるか。芯の太さを調整するように、限られた資源と時間をどう活かすかが、まさに「人事」なのです。
人間には、ただ天命に従うのではなく、それをより良く活かすための“考える頭”があります。ただし、その使い方は人によって大きく異なります。ある人は「どうにもならない」と諦め、ある人は「ではどうすればいいか」と動き出す。その差がやがて、大きな違いになっていくのでしょう。
私自身、今まさに「変えられないもの」と「変えられること」のあいだで日々判断を重ねています。どこまでが天命で、どこからが自分の責任なのか。そこを見極めながら、自分の持つ油を、灯りを絶やさず使い切る。そのような姿勢が求められている気がしてなりません。
静かな夜に、一つの灯火が語ってくれる深い教え。
『二宮翁夜話』が、今日もまた、日々の経営の道しるべになってくれています。