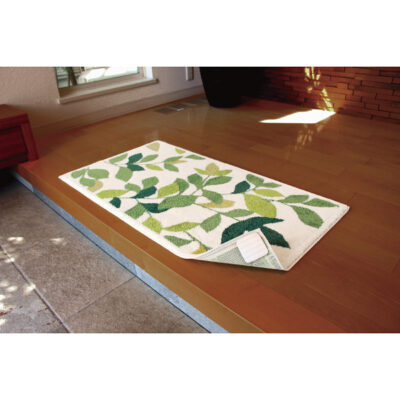よきお客ぶり|7月22日のことです。
Release: 2018/07/22 Update: 2018/07/22
よきお客ぶり
「引き上げぶり」、これは出発にもまして大切なことである。
演説などが、最初の第一声が大切である以上、最後のむすびが肝要である。
噺家などは、出てくる第一声はたいして苦労しない。しかし最後のおとしは、一席のお笑い死生を決定する。
よきお客ぶりというのは、飽かれもせず、早すぎもせず、ちょうどよい潮時に、さっと引き上げて帰る。
7月22日、丸山敏雄一日一話幸せになるための366話、今日の言葉です。
なんでも初めと終わりが重要なことはよく言われることです。
その中でも締めの言葉が重要なんだということがわかります。
噺家が最後の落ちをしくじると大変なことになりますね。
傾聴能力が大事なんですね。人の話を聞くこと。
ちょどよい潮時に話に夢中になっている人の話を締めさせる工夫も必要ですね。
時間は有限なのですから。
今日一日朗らかに安らかに喜んで進んで働きます。
関連コンテンツ
仕事の意味を考える 諸君のおのおのについて、静かにその意味を見極めたまえ。必ずすばらしい高い意味を見出すであろう。 もし、ただ今の仕事に意味なしと知ったら、断然止め給え。 足下を掘って大岩盤石につき当…
我が力を誇る 楽聖ベートーヴェン、文豪シェークスピア、画聖ラファエロに、英雄ナポレオン、聖雄ガンジーに、誰があなたの生命にそうした大天才をしのぐ力が無いとすることができるか。その力は生命より発揮する。…
喜んで税金を納める 喜んで税金を納める人の事業がますます栄え、税を恐れビクビクしたり、いやいやながら納めたり、なるべく納めまいとしたり、期限をおくらせたりする、そうしたけちついた、しみったれた心では、…
四囲の物質は、人を生かし、守り、正しい方向を示し、苦難を脱却せんと不断の努力をつづけている。 心朗らかに働いていれば万事は必ず好転する。 それで事情がどのように悪化しようと、商品が売れず、製品が推積し…
運命はみずから招く 人の一生は、運命という、どうすることも出来ない力で、きまった道筋を引きずられて行くものである、というように信じているものがある。しかし、いやしくも人の関係する仕事で、すておいて、手…