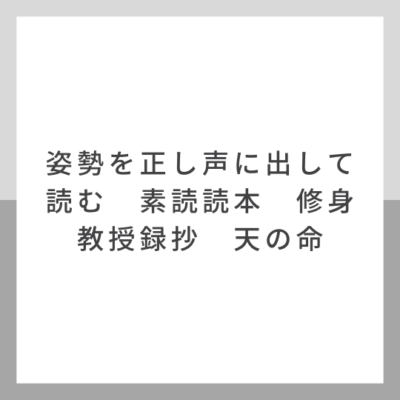下座を行ずる②
Release: 2022/09/24 Update: 2022/09/24
下座を行ずる②
世間がその人の真価を認めず、よってその位置がその人の真価よりはるかに低くても、それをもって、かえって自己を磨く最適の場所と心得て、不平不満の色を人に示さず、わが仕事に精進するのであります。これを「下座を行ずる」というわけです。【417】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
肯定的捉えることを教えるのは簡単ではないですね。
子供の不平不満を聞いてあげるにも必要ですが捉え方一つで変わるということを自分が実践していないから伝わらないのでしょうか。
まずは、継続したこんなことがあるよということが一つでも目に見えればいいのですが。
下座を行ずるということは、まさに肯定的であることが大前提です。
自分の方が以前は上にいたと感じることがすでに否定的な気もします。
何事にも「よしここで鍛錬する」という気持ちがあることはすでに肯定的なことです。
今日は何を鍛錬するかそれは仕事であり学生は勉強というわけです。
これでは伝わらないな(笑)
関連コンテンツ
人生の首尾を押さえる 今「人生を正味三十年」と考えるとなると、それはいわば人生という大魚を、頭と尾で押さえるようなものです。魚を捕らえるにも、頭と尾を押さえるのが、一番確かな捕え方であるように、人生も…
階段を登る工夫③日々の準備 しかしそのためには、非常な精神力を必要とするわけです。階段をさらさらと登るには、二倍の力ではなお足りないでしょう。少なくとも三倍以上の、心身の緊張力持たねばできない芸当です…
職責を通して道を体得する われわれの国家社会に対する努めは、どこまでもその職分を通して行われる外ないわけですが、同時にまた他面、このような考えに対しては、いかなる人間でも、ほとんど例外なく、何らかの職…
われわれ人間というものは、すべて自分に対して必然的に与えられた事柄については、そこに好悪の感情を交えないで、素直にこれを受け入れるところに、心の根本態度が確立すると思うのであります。否、われわれは、か…
思えば私達が、何ら自らの努力によらないで、ここに人間としての生命を与えられたということは、、まことに無上の幸と言うべきでしょう。しかも私達は、これが何ら自己の努力によるものでないために、かえってこの…