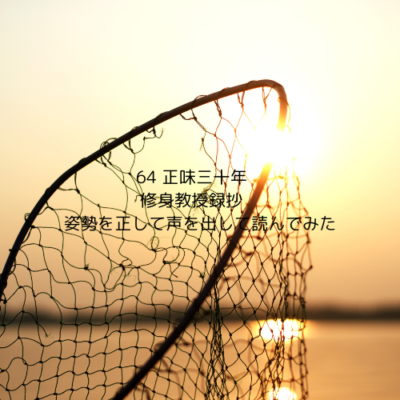二度とない人生を⑬

名・利というものは如何に虚しいものか。しかも人間はこの肉体の在するかぎり、その完全な根切りは不可能といってよい。
先生の数多い著述の中でも、めずらしい「隠者の幻」と題する小説風のものがあります。元東京帝大の教授であった有馬香玄幽先生が、敗戦後、その職を辞し、「全国行脚」に出て山村僻地や炭坑をはじめ恵まれない階層にも身を置くのですが、それさえもある時期に到ってピタリとやめ、京都の比叡山々中の岩窟にて隠者的生活に入るというのが小説のあらすじです。
そしてこの小説のテーマは、結局のところ(一)名利の虚しさであり、(二)名利の完全超脱の難しさであり、(三)真実の道の光を伝える、という三つに帰するのではないかと思われます。
そしてこの有馬香玄幽先生のモデルは誰かということは、いつも問題になることですが、それのお一人は、明治期の隠者的キリスト者の新井奧邃先生であることは間違いないことで、森先生の内にある隠者への憧憬の念、これまた私どもの想像以上のいものがあると言えそうです。
「隠者」という生き方を実践することは、実に難しいことだと感じます。 たとえば、ゴミ拾いやトイレ掃除のような行為にしても、心のどこかに「誰かに気づいてほしい」という思いが残るものです。 その気持ちは決して悪いものではありませんが、究極的には、そうした感情さえも消えて、ただ自然に行える境地こそ「名利を超える」ということなのでしょう。
とはいえ、その境地に至ることは容易ではありません。 森信三先生が「根切り」と表現されたように、人間の内にはどうしても自己顕示の芽があり、それを完全に断ち切ることはほとんど不可能に近い。 だからこそ、先生の言葉には深い味わいと現実感があります。
私自身も、せめて日々の仕事の中で、人より少しでも頑張り、お客様に少しでも喜んでいただく。 そのような小さな実践の積み重ねの中で、名利を超えた何かに近づければと思います。 完全な「根切り」は難しくとも、そこを目指して生きることが、人としての修行なのかもしれません。
#心魂にひびく言葉 #森信三 #寺田一清