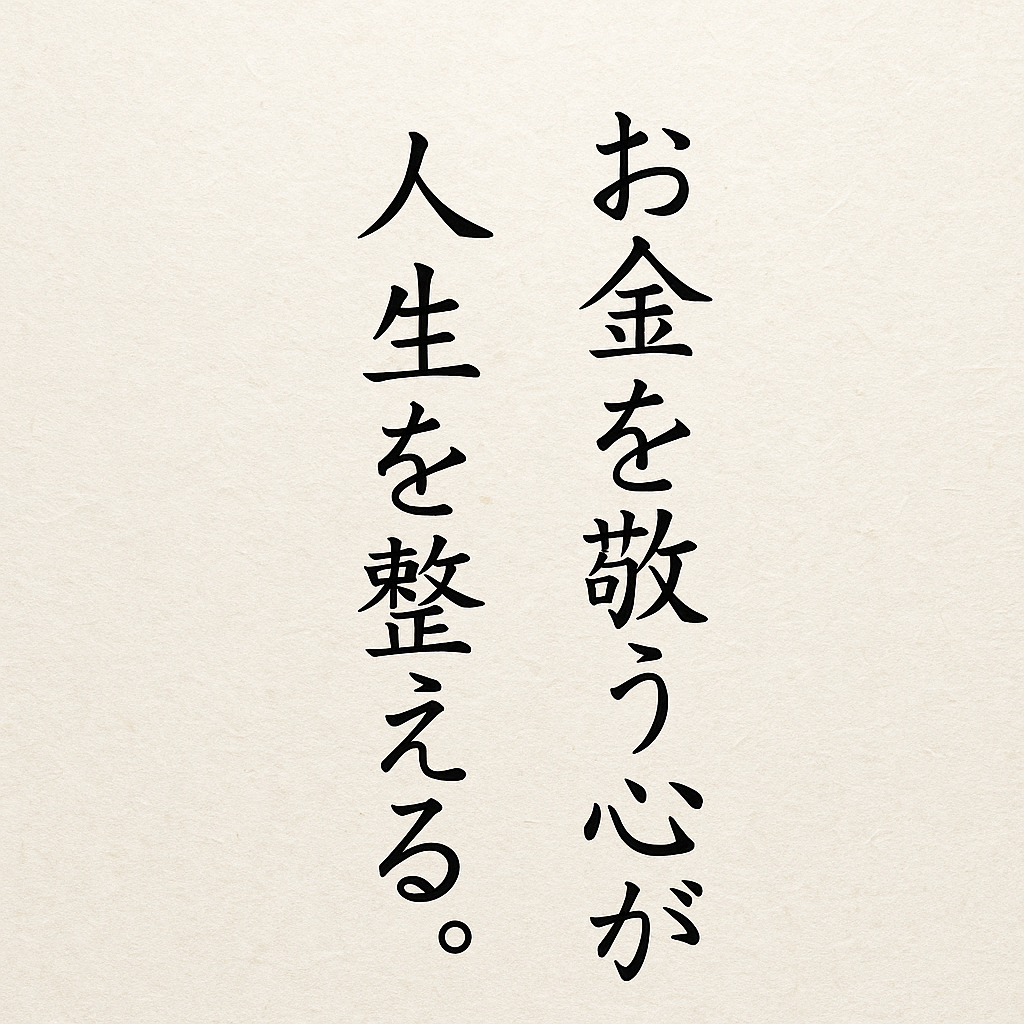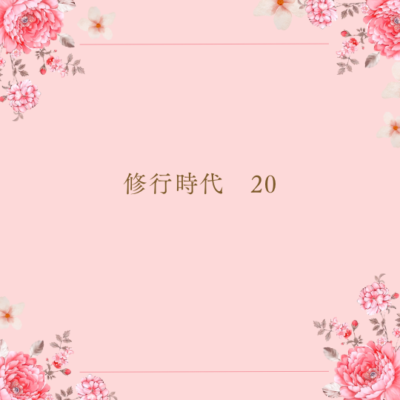二度とない人生を⑯
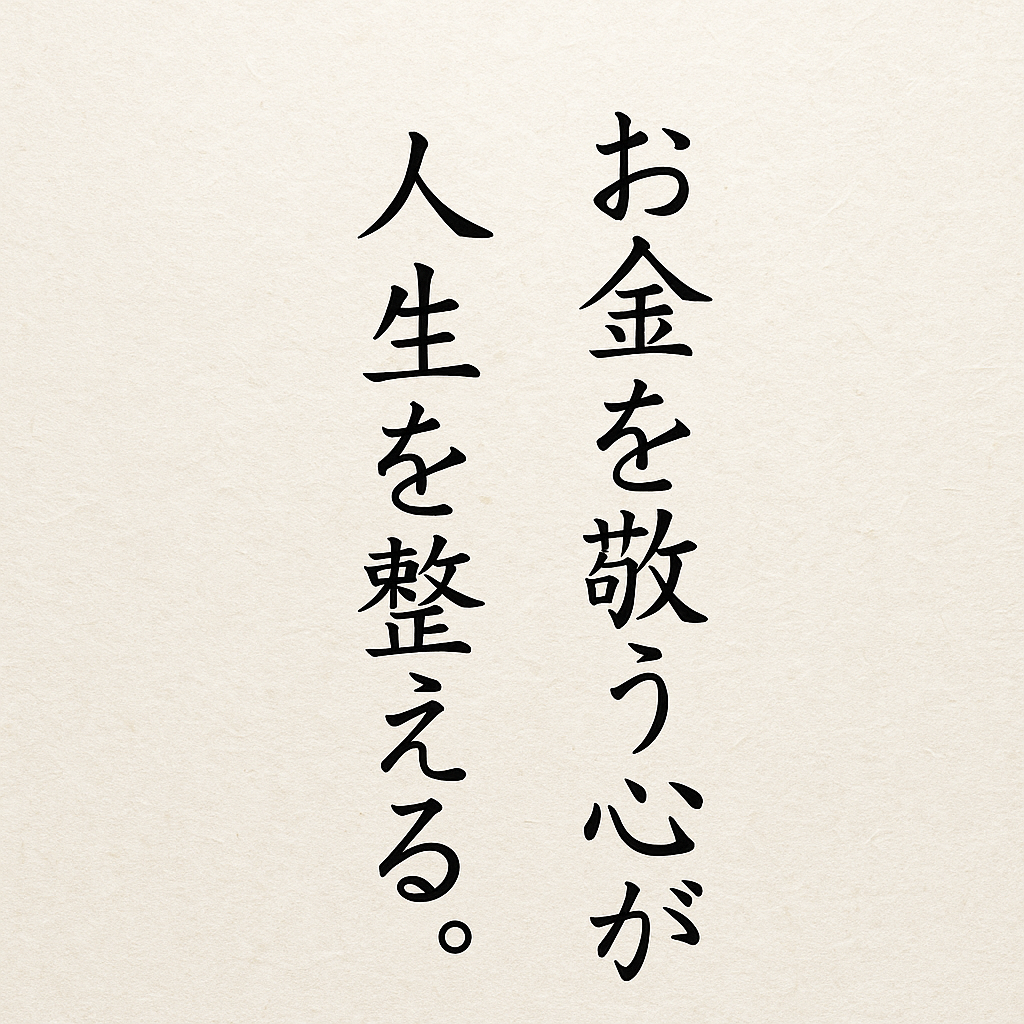
金の苦労を知らない人は、その人柄がいかに良くても、どこか喰い足りぬところがある。人の苦しみの察しがつかぬからである
哲学者の森信三先生の語録に、「お金」に関するものが、意外に多いのにお気付きでしょう。それは、先生にとって当然すぎることで、「真理は現実の唯中にあり」をもって、学問論の根幹とする先生にとって、不思議でも何でもないことです。申すまでもなく、現実界を動かす三大要素は、人・モノ・カネであるからです。
〇お金の苦労によって人間は鍛えられる。
〇お金を軽視する者は、いつかどこかでシッペ返しをうける。
〇たとえお金持ちになれなくとも、お金に困らぬ人間になる義務がある。
〇お札を逆さに入れたり、ハチあわせにしたりせぬこと。
先生は、いつも小銭入れと札入財布のほかに、木製の特製胴巻に、まとまった一万円札を入れておられたようです。イザという時の用意の周到さは明治人の気骨とも言えましょう。
お金を雑に財布に入れている自分にとっては、まさに痛い言葉です。 しかし、苦しくなると数字から目をそむけたくなる自分がいるのも確かです。 もちろんお金の重要性は理解しているつもりですが、形として丁寧に扱うこと―― それもまた心の在り方の一つなのだと思います。
子どもたちが巣立てば少し楽になるかと思いましたが、実際にはそう簡単ではありません。 何かと出費が重なり、常に気を配らなければなりません。 お金は生きる上で避けて通れないものであり、挑戦や新しいことにも必ず必要となる。 だからこそ、苦労が尽きることはないのです。
「お金に困らぬ人間になるのは義務である」という先生の言葉は、単なる経済的な意味を超えて、 人としての自立の姿勢を説かれているのだと思います。 お金に振り回されず、しかし軽んじることなく、 感謝と慎みをもって扱う――そのような生き方を心がけたいと思います。