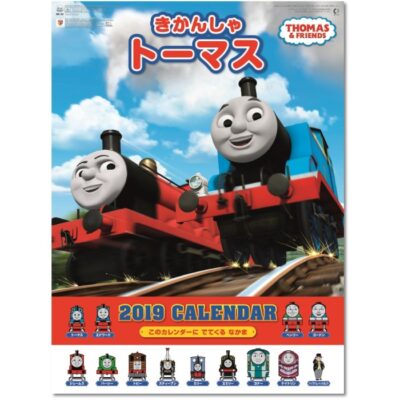人の患は、好んで人の師となるに在り|5月12日のことです。
Release: 2018/05/12 Update: 2018/05/12
人の患は、好んで人の師となるに在り
人の患は、好んで人の師となるに在り。(離婁上二十三章)
ひとのうれいは、このんでひとのしとなるにあり。(りろうかみにじゅうさんしょう)
【訳】
人間の悪い癖は、とかく他者の先生になりたがることである。
孟子一日一言、5月12日、今日の言葉です。
そうかもしれませんね。
人に何かを教えるときは自分が学ばせてもらってもらっているということを忘れはいけませんね。
実際に教える人が一番学ばせていただいているということがあります。
アウトプットすることにより自分が教えられる。
仕事はかならず誰かに教えることがともないますからその時は自分が学ばせてもらっていると思わなければなりませんね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
時を待つ 齊人の言へることあり。曰く、智慧ありと雖も勢に乗ずるに如かず、鎡期ありと雖も時を待つに如かずと。(公孫丑上首章) せいひといえることあり。いわく、ちえありといえどもいきおいにじょうずるにしか…
若し薬瞑眩せずんば厥の疾瘳えず。(滕文公上首章) もしくすりめいげんせずんばそのやまいいえず。(とうぶんこうじょうしゅしょう) 【訳】 薬は飲んでめまいがする位でないと、病気は治らない(本気の努力をす…
本を一にせしむ 天の物を生ずるや之れをして本を一にせしむ、而るに夷子は本を二にする故なり。( 滕文公上第五章) てんのものをしょうずるやこれをしてもとをいちにせしむ、しかるにいしはもとをににするゆえな…
其の心に作れば其の事に害あり。其の事に作れば其の政に害あり。聖人復た起るも吾が言を易へじ。(とうぶんこうしもきゅうしょう) そのこころにおこればそのことにがいあり。そのことにおこればそのまつりごとにが…
覇者の民―驩虞如・王者の民ー皥々如 覇者の民は驩虞如たり。王者の民は皥々如たり。(尽心上十三章) はしゃのたみはかんぐんじょたり。おうじゃのたみはこうこうじょたり。(じんしんかみじゅさんしょう) 【訳…