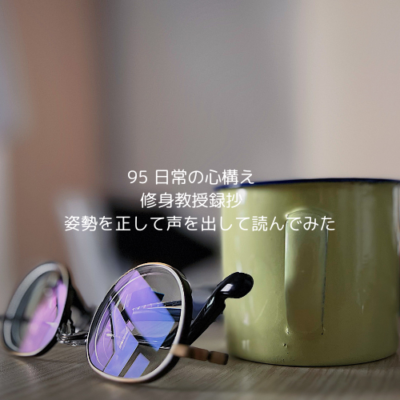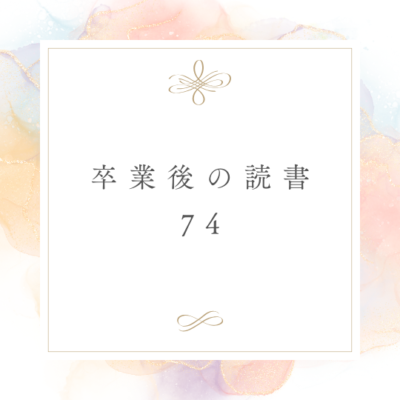学問修養には気魄を要す
Release: 2022/03/23 Update: 2022/03/23
学問修養には気魄を要す
古人の学と言えば、必ず聖人たらんことを志したものです。しからば今日われわれ日本人として、いやしくも学問修養に志す以上、われわれのもつ偉大な先人の踏まれた足跡を、自分も一歩なりとも踏もうと努め、たとえ一足でも、それににじり寄ろうとする気魄がなくてはならぬと思うのです。【316】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
しかし、教授の授業を実際うけた人の本を探してみたくなりましたね。
40歳までに一冊の本を書いた教師がいたのでしょうか。
実に気になるところです。
人を雇うということは実際教育というか教えなくてはならないことがたくさんありますが、その軸というものがずれてくると問題が多いと感じます。
やはり、自分自身だけのためというのはいささかみっともない気もします。
仕事というのは人のためだったり世の中のためだったりしますからね。
もうすぐ四月ですから計画しないといけませんね。いろいろと。
関連コンテンツ
諸君は階段を登るとき、まるで廊下でも歩くように、さらさらと登る工夫をしてごらんなさい。というのも人間の生命力の強さは、ある意味ではそうしたことによっても、養われると言えるからです。 階段の途中に差し…
性欲の問題についてですが、まず根本的に考えねばならぬことは、性欲は人間の根本衝動の一つだということです。すなわちこれを生理的に言っても、性欲は人間の生命を産み出す根本動力だと言えます。その意味からは、…
隠岐の「学聖」と言われた永海佐一郎先生という方は、「人間の真のネウチはどこにあるのか」という問題について、次のような定式を立てておられます。仕事への熱心さⅩ心のキレイさ=人間の価値 #運命を創る100…
そのような根気というものは、一体どこから出るからというに、結局はそれは母親のわが子に対する慈愛の一念の他ないといってよいでしょう。そしてそれを子どもに躾ける上において大事な一転は、自分自身が主人から…
わたくしの考えでは、学窓を出た直後からほぼ十年間の読書は、ほとんどその人の生涯の歩みを、決定するとさえ言えるであろう。 運命を創る100の金言 学生から出て読んだ本を考えてみると、どちらかというとビジ…