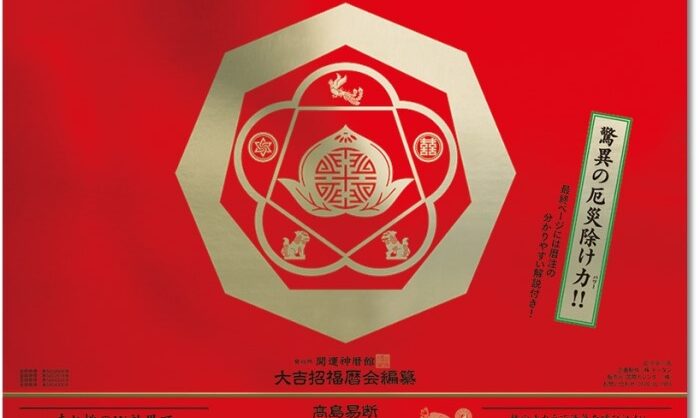教誨するを屑しとせざることも|10月2日のことです。
Release: 2018/10/02 Update: 2018/10/02
教誨するを屑しとせざることも
教えも亦術多し。予れ之れを教誨するを屑しとせざることも、是れ亦之れを教誨するのみ。(告子下末章)
おしえもまたじゅつおおし。われこれをきょうかいするをいざぎよしとせざることも、これまたこれをきゅうかいするのみ。(こくししもまつしょう)
【訳】
教育の方法を色々ある。私が、これは教えるべきではないとして教えないということも、(相手に反省させるためであるから)これもまた立派な教育方法である。
10月2日、孟子一日一言の言葉です。
教えないことも教育。
そういうこともあるかもしれませんね。
しかし、時代によって変わるのが教育というもので今の場合は教えないことは伝わらないといこともあります。
使い分けが必要ですね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
今の所謂良臣は古の所謂民族なり 「我能く君の為に土地を平辟き、府庫を充たす」と。今の所謂良臣は古の所謂民族なり。君道に郷はず仁に志すして、之れを富まさんことを求む。(告子下九章) 「われよくきみのため…
義ー長ずるもの・長とするもの 長ずるもの義か、之を長とするもの義か。(告子上四章) ちょうずるものぎか、これをちょうとするものぎか。(こくしかみよんしょう) 【訳】 (孟子がいわれた)「(告子も、年長…
道を同じうす 禹・稷・顔回同じうす。(離婁下二十九章) う・しょく・がんかい、みちをおなじゅうす。(りろうしもにじゅうきゅうしょう) 【訳】 禹・后稷・顔回は行ったことは(表面上はちがっていたが)、そ…
尚友 其の詩を頒し、其の書を読みて、其の人を知らずして可ならんや。是れを以て其の世を論す。是れ尚友なり。(万章下八章) そのしをしょうし、そのしょをよみて、そのひとをしらずしてかならんや。これをもって…
眸子より良きはなし 人に存する者は眸子より良きはなし。(中略)其の言を聴きて其の眸子を観れば、人の焉んぞ廋さんや。(離婁上第十五) ひとにそんするものはぼうしよりよきはなし。(ちゅうりゃく)そのげんを…