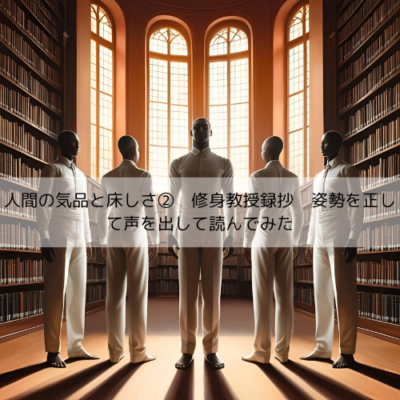書物を撫でる
Release: 2022/05/13 Update: 2022/05/13
書物を撫でる
諸君、書物というものは、ただ撫でるだけでもよいのです。ちょっとでも開いてみればさらによろしい。それだけでも功徳のあるものです。つまりそれだけその本に縁ができるからです。いわんや一ページでも読んだとしたら、それだけ楔を打ち込んだというわけです。【137】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
書物を撫でる。なんともよい表現だと感じます。
そういう意味では撫でまくっているかもしれません。
今年は教授で攻めるということは決まっていますので毎日少しづつ読んで1年くらいたったらしばらく放置してまた読むということの実践をしてみたいと思っています。
しかし、こういう言葉が体から出てくるようになるためには相当の読書の量が必要だと思いますし考えなければいけないと思います。
人に教える立場にある人というのはどういう頭の構造なんでしょうか。
伝えることを実行というのであればそれが仕事である人は覚えられるような気がしますし、凡人は誰かにつぶやく程度のことは常にしていないといけないですね。
関連コンテンツ
卑屈と功利打算 そもそも私達が、一つの徳目を真に徹底的に履み行わんがためには、結局根本において、人格の転換を必要とすると言えましょう。たとえば人が傲慢に振舞うということは、畢竟するに、その人が調子に乗…
プラス・マイナスは裏表 人生の事すべてプラスがあれば必ず裏にはマイナスがあり、表にマイナスが出れば、裏にはプラスがあるというわけです。実際神は公平そのものですが、ただわれわれ人間がそうと気付かないため…
人間の締りというものは、ある意味から申せば、その人が家庭において、如何に心を引き締めているか、その心構えの反映といってもよいでしょう。例えば弁当箱ひとつにしても(一)家へ帰れば、自分の弁当箱だけはす…
人間としての嗜み 諸君らは、傘をさして歩くときは、斜めに肩をもたせかけたりなどしないで、柄を垂直にしてさすものです。また天気になったらキチンと畳んで、柄の先が地面を引きずらないようにするのです。 なお…
人生の峠路 諸君たちは、その欲すると欲せざるとにかかわらず一日一日、否、一刻一刻、この人生の峠路に向かって歩みつつあるのであり、実はその一歩一歩が、諸君らの方向を決定しつつあるわけです。【43】 #修…