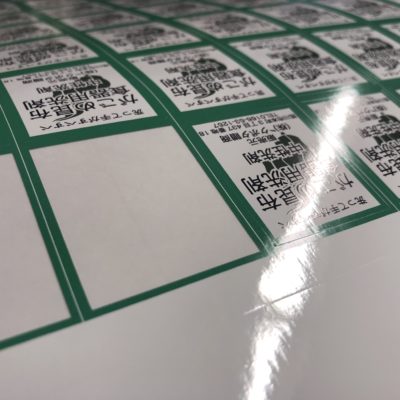杖つきて立つは、飢(う)うるなり。汲みて先ず飲むは、渇(かつ)するなり。(行軍)|4月30日
Release: 2020/04/30 Update: 2020/04/30
杖つきて立つは、飢(う)うるなり。汲みて先ず飲むは、渇(かつ)するなり。(行軍)
杖而立者、飢也。汲而先飲者、渇也。
「敵の将兵の中で、杖をついている者が多いのは、兵糧が不足していて、敵兵が飢えて体が弱っている証拠である。
水を汲みに出るや、運ぶより先に飲もうとするのは、水不足のために敵兵の喉が渇いて弱っている証拠である」
杖をつくとは、ここでは兵器を杖として立っているという意味。
水を汲みに行った兵士が運ぶ前にまず飲むことを確認するとは、孫子も観察がこまかい。
4月30日、孫子・呉子一日一言の言葉です。
おはようございます。
ここでもやはりよく観察することが大事。
スパイも重要になっていますね。
敵を分析するためには信頼のおけるスパイが必要です。
しっかりと情報を取集してくる、それを分析する。
とても大事なことですね。
今日も一日がんばります
関連コンテンツ
兵法は、一日に曰く度、二に曰く量、三に曰く数、四に曰く称、五に曰く勝。(軍形) 兵法、一日度、二日量、三日數、四日稱、五日勝。(地生度,度生量,量生数,数生称,称生勝。) 「兵法には次の五つの要素があ…
兵を用うるの法、其の来らざるを恃むこと無く、吾を以て待つ有るを恃むなり。(九変〉 用兵之方、無恃其不来、恃吾有以待也。(無恃其不攻、恃吾有所不可攻也。) 「戦争にさいしては、敵が来襲しないように期待を…
善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政(まつりごと)を為す。(軍形) 善用兵者、修道而保法。故能為勝敗之政。 「いくさ上手な者はよい政治を行ない、法令を整備し、これをきちんと守らせる…
三軍の衆、必ず敵を受けて敗無からしむべきは、奇正是れなり。(兵勢) 三軍之衆、可使必受敵面無敗者、奇正是也。(兵之所加、如以暇投卵者、虚賞是也。) 「全軍に敵を迎え入れて必勝の結果を得るようにさせるに…
我出でて利あらず、彼も出でて利あらざるを支と曰う。支形(しけい)は、敵、我を利すと雖も、 我出而不利、彼出而不利曰支。支形者、敵雖利我、(我無出也。引而去之。令敵半出而撃之利。) 「味方にとっても敵に…