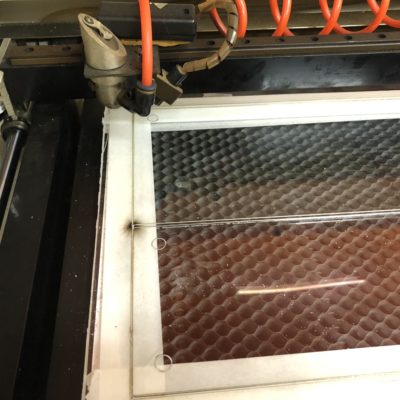正々の旗を邀(むか)うること無かれ。堂々の陣を撃つこと勿(な)れ。此れ変を治る者なり。(軍争)|3月31日
Release: 2020/03/31 Update: 2020/03/31
正々の旗を邀(むか)うること無かれ。堂々の陣を撃つこと勿(な)れ。此れ変を治る者なり。(軍争)
無邀正正之旗,勿擊堂堂之陣,此治變者也。
「隊伍を整えて自信を以て進撃してくる敵を迎えうつべきではない。
堂々たる陣を張っている敵とは正面衝突を避けるべきである。
こういう者と戦うときには奇策を用いて敵の意表をつく。これが変を治めるということである」
以上で”気を治める””心を治める””力を治める””変を治める”という四つの戦闘の要領を説明している。
3月31日、孫子・呉子一日一話(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
おはようございます。
敵がしっかりしている時は戦うべきではない。
ということでしょうね。
正面から正々堂々と戦うことは避けた方がよさそうです。
常に意表をつくような仕掛けがないと敵の乱れを誘えない。
戦局を動かすためには常に奇策が必要ですね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
軍の擾(みだ)るるは、将の重からざるなり。(行軍) 軍擾者、将不重也。 「軍に秩序がなく、統制を欠いて乱れているのは、指揮官が無能で威厳が備わっていない証拠である」”将”とは将軍のこと。ここではその部…
疾(と)く戦えば則ち存(そん)し、疾く戦わざれば則ち亡ぶるものを、死地と為す。(九地) 疾戦則在、不疾戦則亡者、為死地。 「速やかに戦えば生存できる可能性はあるが、速やかに戦わなければ全滅する恐れがあ…
夜呼ぶは、恐るるなり。(行軍) 夜呼者、恐也。 「夜になって、敵軍が大声で呼び交わす声が聞こえるのは、敵がなにかにおびえているからである」夜中に敵が大声を出して呼び合っているのには、さまざまな理由が考…
故に兵を知る者は、動いて迷わず、挙げて窮せず。(地形) 故知兵者、動而不迷、拳而不窮。 「だからいくさのことをよく知っている者(すなわちいくさ上手)は、味方、敵、地形を三つ完全に把握しているので、一度…
将、敵を料(はか)ること能わず、少を以て衆を合せ、弱を以て強を撃ち、兵に選鋒無きを北と曰う。(地形) 将不能料敵、以少合衆、以弱撃強、兵無選鋒曰北。 「将軍が敵の力を正当に評価できない、少数の兵力をも…