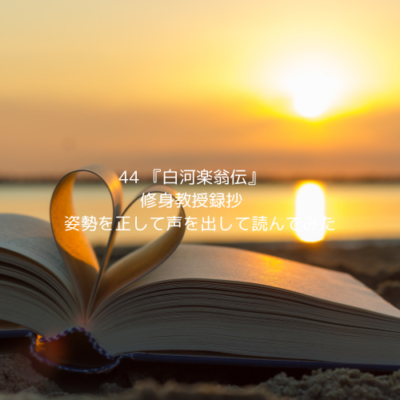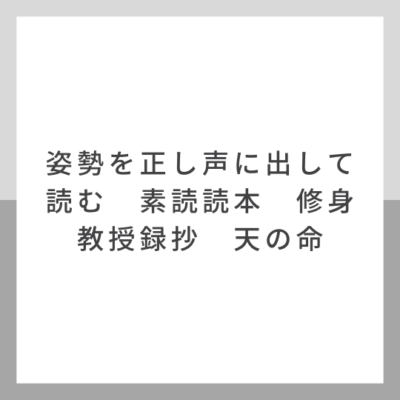目下の人に対する心得
Release: 2022/09/23 Update: 2022/09/23
目下の人に対する心得
目下の人に対する心得の一つとして、目下の人だからといって、言葉遣いをぞんざいにしないように。ーーということでしょう。これはうっかりすると気付きにくい点ですが、大体人間の人柄というものは、その人が目下の人に対する場合の態度、とくにその言葉遣いによって分かるものであります。【224】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
この言葉遣いという点に気を付けなければいけません。
考えるより先に言葉が出てしまうような場合があります。
ほとんどの場合は怒りが多い。
特に仕事の場合においては、目下の人のミスというものがあります。
その時の自分の感情がどうなっているのかを客観的に考えなくてはいけません。
笑ってごまかすというような場面もあります。
そういった場合も目上に立つものは言葉遣いに細心の注意をもっていかねばなりません。
失敗したその経験をしっかりと次回に生かすこと。
これが一番重要項目です。
関連コンテンツ
では、私が諸君らに対してこの本をお奨めするのは、一体いかなる意味においてでしょうか。それというのも諸君らも知ってのように、この楽翁公という人は、決して普通の意味での教育者ではないからです。楽翁公につ…
生理と精神 生まれつきとしては、肉体的にいかに強壮な人でも、もしその人が性欲を守る点できびしくなかったら、将来必ずや衰える期がくるのであります。同時にまたこれに反して、その生まれつきとしては、さまで健…
プラスの裏にマイナスあり 人間は、順調ということは、表面上からはいかにも結構なようですが、実はそれだけ人間が、お目出たくなりつつあるわけです。すると表面のプラスに対して、裏面にちゃんとマイナスがくっつ…
われわれ人間というものは、すべて自分に対して必然的に与えられた事柄については、そこに好悪の感情を交えないで、素直にこれを受け入れるところに、心の根本態度が確立すると思うのであります。否、われわれは、か…
宗教・哲学の役割 自分の情熱を深めていくには、一体どうしたらよういかというに、それはやはり偉人の伝記を読むとか、あるいは優れた芸術品に接することが、大きな力になることでしょう。そしてそれを浄化するには…