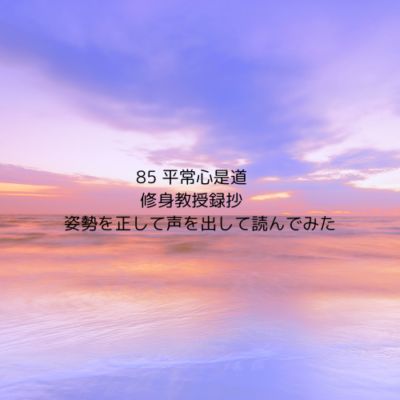置土産
Release: 2023/01/17 Update: 2023/01/17
置土産
今諸君らの生活が、真に深く、かつ内面的に大きかったならば、諸君らの精神は、必ずや後に来る人々のために、一種の置土産となることでしょう。さらにまた、私共のように教職にある者としては、その精神は、仮にその学校を去る時がありましても、もしその生活が真実であったならば、必ずや後に多少の余韻が残るようでなくてはなりますまい。【516】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
生きれば死に、来れば去る。
そのように循環しているわけですが平常すぐに忘れます。
実際、熱を出したりよか様々に体調を崩しても死ぬとは思っていないわけです。
現実を見ないようにしてしまうものです。
真実に生きるというのは、やり残しのない一日をいかに過ごそうとするかということかもしれません。
場を自分がもっているのに精一杯にならないのは問題が多い。
なんだか反省です。
関連コンテンツ
日常の雑事雑用をいかに巧みに要領よくさばいていくか。そうしたところにも、人間の生き方の隠された呼吸があるということです。 #運命を創る100の金言 #森信三 雑事雑用の撲殺されている毎日ですが、要領よ…
ところで人間は、この「暑い」「寒い」と言わなくなったら、そしてそれを貫いて行ったとしたら、やがては順逆を越える境地にも至ると言ってよいでしょう。ここに私が順逆というのは、ていねいに言えば「順境逆境」…
人間形成の三大要素 人が自分を内省して、少しでも自分の真実の姿を求めるようになるには、まず道を知るということと、次には苦労するという、この二つのことが大切だと思うのです。 すなわち人間は、道すなわち教…
叡智の源 真の叡智とは、自己を打ち越えた深みから照らしてくる光であって、私達はこの光に照らされない限り、自己の真の姿を知り得ないのであります。【80】 #修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日…
人生を深く生きるということは、自分の悩みや苦しみの意味を深く噛みしめることによって、かような苦しみは、必ずしも自分一人だけのものではなくて、多くの人々が、ひとしく悩み苦しみつつあるのだ、ということが…