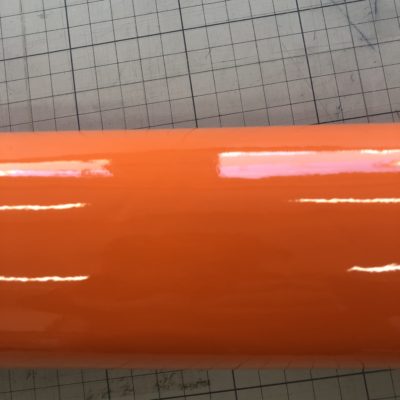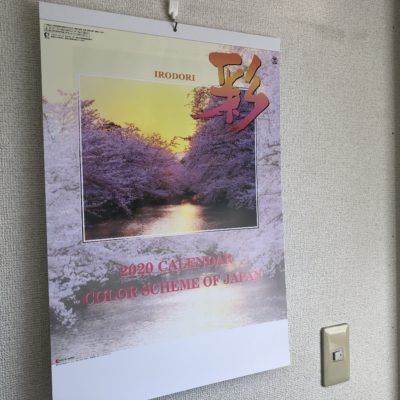能く敵人にして自ら至らしむるは、これを利すればなり。(虚実)|2月28日
Release: 2020/02/28 Update: 2020/03/01
能く敵人にして自ら至らしむるは、これを利すればなり。(虚実)
能使敵人自至者、利之也。(能使敵人不得至者、害之也、故敵供能勢之、飽能識之、安能動之,出其所不趨,趨其所不意。)
「敵を引き寄せるためには、利でつることだ。(作戦を思いとどまらせるには妨害することだ。敵にゆとりがあれば奔命に疲れさせる。敵の兵量が十分なときは糧道を断つ。敵が冷静なときはかき乱す。敵の来ない所に行き、敵の意表をついて打って出る)。」
能く敵人をして至るを得ざらしむるは、これを害すればなり。故に敵佚すれば能くこれを労す。飽けば能くこれを饑えしめる。安んすれば能くこれを動かす。其の趨らざる所に出て、其の意わざる所に趨る。
2月28日、孫子・呉子一日一言(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
関連コンテンツ
急に暴にして而る後に其の衆を畏るるは、不精の至(いた)りなり。 先暴而後畏其衆者、不精之至也。 「最初はどなり散らしたりして手荒く部下を使い、あとで離反を恐れてご機嫌をとったりするのは、上の者が下の者…
凡(およ)そ兵を用(もち)うるの法、国を全うするを上と為し、国を破るはこれに次ぐ。(諜攻) 凡用兵之法、全国為上、破国次之。(全軍為上、破軍次之。全旅為上、破旅次之。全卒為上、破卒次之。全伍為上、破伍…
夫れ勢い均しきとき、一を以て十を撃つを走と曰う。(地形) 夫勢均、以一撃十曰走。 「彼我両軍の勢力が拮抗しているとき、一の力で十の力の敵と戦う羽目に陥ったばあいは、これを敗走するというのである」謀攻篇…
其の戦いを用うるや、勝つも久しければ、則ち兵を鈍らせ鋭(えい)挫(くじ)く。(作戦) 其用戦也、勝久則鈍兵挫鋭。(攻城則力屈。久暴師則国用不足。) 「十万の大軍が敵と戦えば、たとえ勝つとしても、戦いを…
来たりて委謝(いしゃ)するは、休息を欲するなり。(行軍) 来委謝者、欲休息也。 「敵の方から軍使をつかわして、おだやかに挨拶してくるのは、一休みして時間かせぎしようとしている証拠である」ここの”来たる…