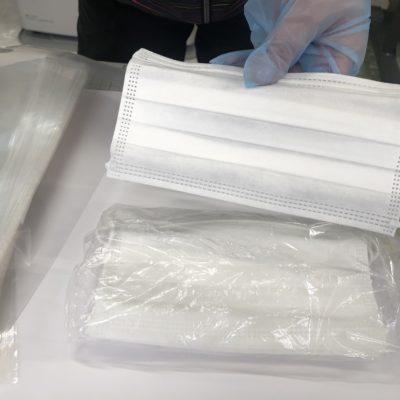辞(ことば)卑(ひく)くして備えを益すは、進まんとするなり。辞強くして進駆(しんく)するは、退かんとするなり。(行軍)|4月27日
Release: 2020/04/27 Update: 2020/04/27
辞(ことば)卑(ひく)くして備えを益すは、進まんとするなり。辞強くして進駆(しんく)するは、退かんとするなり。(行軍)
辞卑而益備者、進也、辞強而進駆者、退也。
「敵の軍使が口ではへりくだったことをいいながら、一方では着々と守りを固めているのは、実は進攻の意図をもっているのである。
敵の軍使が、強気一点張りのことをいい、いまにも攻めて来そうな構えを示すおは、その実退却しようとたくらんでいるのである。」
敵の軍使の態度や口上で、その実情を判断する方法である。
軍使として来る以上は、相当の者で、なんとかわが方をたぶらかそうとする。その逆をつくのである。
4月27日、孫子・呉子一日一話(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
おはようございます。
騙されてはいけませんね。
たぶらかしにきます。
向うの軍使が敵である方にくるというのは常に何かある。
ここで考えるのはいかに戦わないで勝つか。
常、目的は被害が最小で勝つこと。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
善(よ)く兵を用(もち)うる者は、人の兵屈(へいくつ)するも、戦うに非ざるなり。人の城を抜くも、(謀攻) 善用兵者、屈人之兵、而非戦也、抜人之城、(而非攻也、毀人之国、而非久也。必以全争於天下。故兵不…
彼を知り己を知れば、百戦して殆(あや)うからず。彼を知らずして己を知れば、一勝一負(いっしょういっぷ)す。(謀攻) 知彼知己者、百戦不殆、不知彼而知己、一勝一負。(不知彼不知己、毎戦必殆。) 「敵を知…
衢地(くち)には則ち交じりを合わす。(九地) 衢地則合交。 「衢地にあっては、外交交渉に力を入れ、他国と友好を結ぶべきである」”衢地”とは、交通の要衝で、各国の勢力が浸透し合っている地域である。このよ…
丘陵・隄防には、必ず其の陽に処りて、これを右背にす。此れ兵の利、地の助けなり。(行軍) 丘陵隄防、必処其陽、而右背之。此兵之利、地之助也。 「丘陵や堤防に陣をしく場合には、必ずその日の当る所、すなわち…
勝ちを知るに五有り。以て戦うべきと以て戦うべからざるとを知る者は勝つ(謀攻) 知勝有五、知可以戰與不可以戰者勝。(識衆寡之用者勝。上下同欲者勝。以虞待不虞者勝。將能而君不御者勝。此五者知勝之道也。)…