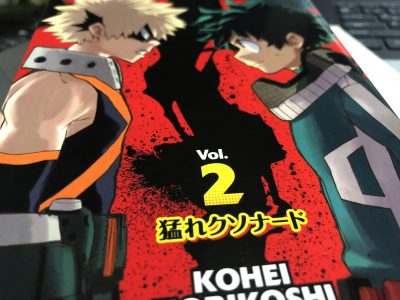天下を有つ|7月2日のことです。
Release: 2018/07/02 Update: 2018/07/02
天下を有つ
匹夫にして天下を有つ。(中略)世を継ぎて以て天下を有つ。(万章上六章)
ひっぷにしててんかをたもつ。(中略)よをつぎてもっててんかをたもつ。(ばんしょうかみろくしょう)
【訳】
身分の低い者でありながら、天下をたもつようになる者(中略)親から世を受け継いで天下をたもつ者。
〇松陰は、「低い身分から王となった者、皆徳があり運に恵まれたから、困難な状況を乗り切ることができた。これは何も天子のことだけではない。武士の俸禄も先祖の苦労と功績のお蔭である。よれをよく考え、今の生活を深く反省するべきである」と記している。
7月2日、孟子一日一言の本日の言葉です。
今の生活が先祖の苦労の元にある。
たしかにそうです。今の生活が自分の力だけで成り立っていることなどはありませんね。
たくさんの過去積み重ねが今の状態のわけです。
実際いつなくなってもおかしくないんです。
先祖から脈々と続く過去のが今。
戦争があったり、天変地異の災害があっても残ってきたわけですから感謝しなければなりませんね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
一朝の患なきあり 此に人あらんに、其の我れを待つに横逆を以てすれば、則ち君子は必ず自ら反するなり。(離婁下二十八章) ここにひとあらんに、そのわれをまつにおうぎゃくをもってすれば、すなわちくんしはみず…
廉・恵・勇を傷る 以て取るべく、以て取るなかるべし。取れば廉を傷る。以て与ふべく、以て与ふることなかるべし。与ふれば恵を傷る。以て死するなかるべし。死すれば勇を傷る。(離婁下二十三章) もってとるべく…
山径の蹊間―用ふれば路を成す 山径の蹊間は介然之れを用ふれば路を成す。為間も用ひざれば則ち茅之を塞ぐ。今は茅、子の心塞げりと。(尽心下二十一章) さんけいのけいかんはしばらくこれをもちうればみちをなす…
恭・敬 難きを君に責むる、之れを恭と謂ひ、善を陳べ邪を閉づる、之れを敬と謂ひ、吾が君はずと謂ふ、之れを賊と謂ふ。(恭・敬) かたきをきみにせむる、これをきょうといい、ぜんをのべじゃをとづる、これをけい…
未だ仁にして 未だ仁にして其の親を遺つる者はあらざるなり。未だ義にして其の君を後にする者はあらざるなり。(梁恵王上首章) いまだじんにしてそのおやをすつるものはあらざるなり。いまだぎにしてそのきみをあ…