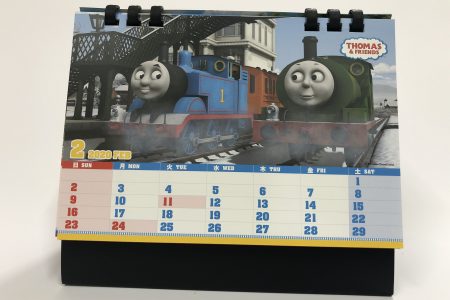一日に二回揮毫(きごう)する|10月12日のことです。
Release: 2018/10/12 Update: 2018/10/12
一日に二回揮毫(きごう)する
起床・洗面の後、東天を拝し、おもむろに筆硯(ひっけん)に対して正坐揮毫(せいざきごう)の三十分間、また就寝前の一時間、全く一日の労を忘じて机に向かい、左に古人の法帖を開き、右に純白の紙をのべる。
ここに己に生活や仕事とは全く別な、静寂閑雅(せいじゃくかんが)、悠々自適(ゆうゆうじてき)の天地が開けてまいります。
書道を学ぶということは、ありのままの自己を、書という形に表して、鍛錬し、反省し、彫琢し、愛玩し、撫育いたしてゆくことであります。これが書道のほんとうの意味だと思います。
10月12日、丸山敏雄一日一話幸せになるための366話、今日の言葉です。
書道の心得はありませんが、自分に向き合う時間を作るという事は大事ですね。
手で何かを書くといことが実際少なくなっていますね。
漢字も数字も忘れています。
自分の字が汚くなってもいますので習い事をするのもいいかもしれません。
今日一日朗らかに安らかに喜んで進んで働きます。
関連コンテンツ
一人の明朗な心境は、その人の肉体健康の元であり、家庭健康の中心であり、事業健康の根源である。 一日の一分も曇らしてはならぬのは、人の心である。 朝はほがらかにに起き、昼はほがらかに働き、夜はほがらかに…
パッととび起きる さあ今から一日の仕事が始まるぞと、ぱっと目をさました。 人は、イキをするのも、食物を消化するのも、血がめぐるのも、すべて自分の力ではありません。自分では知らぬ大自然の力で、眠らされ、…
母親の胎内に十カ月のやすらぎの成長を遂げると、呱々の声と共に、外界に生まれ出てくる。 その時、肉体は別になるが、呼吸のリズムは、母親と同じ調子に、ちょうど時計のネジをかえられたようにキチキチと同じセコ…
人間は発電体 中国地方に、実業家があった。あるところまで成功すると我がままが出、身体をそこね、事業も一気に下りはじめた。 ふとした事から、「君の滅入った心が、事業をだめにする。さびしい心が、人を寄せつ…
仕事が面白い 遠路を歩んで疲れそうになると、歌を歌う。田植えの時でも、「今日はこれだけは」と必死になる時、田植え歌を始める。すると、急に能率があがり疲労も少ない。 それは仕事が面白くなるからである。す…