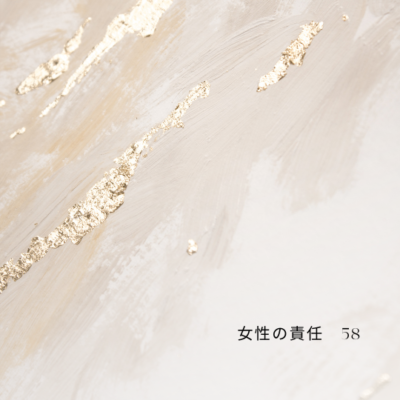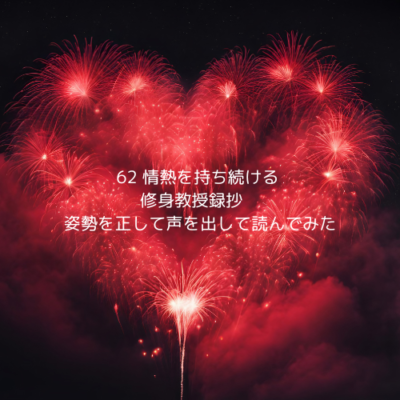不滅なる精神
Release: 2022/06/20 Update: 2022/06/20
不滅なる精神
われわれ人間は、その人の願いにして真に真実であるならば、仮にその人の肉体が生きている間には実現せられなくても、必ずやその死後に至って、実現せられるものであります。否、その志が深くておおきれば、それだけその実現には時を要して、多くはその肉体の死してのち、初めてその実現の緒につくと言ってもよいでしょう。そしてこれがいわゆる「不滅なる精神」、または「精神の不滅」と呼ばれるものであります。【299】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
大きな志は自分の死後にまでも引き継がれるということを考えた時、教授のことを思い出してしまいますね。
教授の言う教育とはそのような大きな志をもった人間を作り出すことが目的なんでしょうね。
自分が死んでから志をもつことの重要性を伝え続けていくというのはやはり文章ですね。
いかに文章に思いを込めて発するかということに尽きるようにも感じます。
あふれ出る言葉を持つことは読書量ということにもなるかと思います。
実践しながら読書をすることが必要ですね。
関連コンテンツ
歩き方と人間の格① 人間いつまでも、ああいうふうに歩いているようでは駄目ですね。(この時、授業時間にもかかわらず、廊下をペタペタと、スリッパを引きずってゆく生徒の足音が、騒々しく聞こえてくる)。内でこ…
尊敬する人は尊敬される人 人々から尊敬されるような人は、必ず自分より優れた人を尊敬しているものです。【486】 #修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新 何かを求め…
女性の弛緩は民族の弛緩となり、女性の変質は民族の変質につながります。民族の将来は女性のあり方如何によって決まると言っても決して過言ではないわけです。 #運命を創る100の金言 #森信三 時…
かくして情熱というものは、人間の偉大さを形づくりところの素材であり、その基礎と言ってもよいでしょう。したがってまた初めから情熱のない干からびたような無力な人間は、いわば胡瓜のうらなり見たいなもので、…
真実に願うことは叶う そもそも世の中のことというものは、真実に心に願うことは、もしそれが単なる私心に基づくものでない以上、必ずやいつかは、何らかの形で成就せられるものであります。このことは、これを信じ…