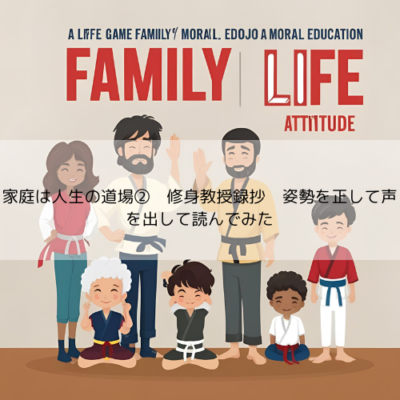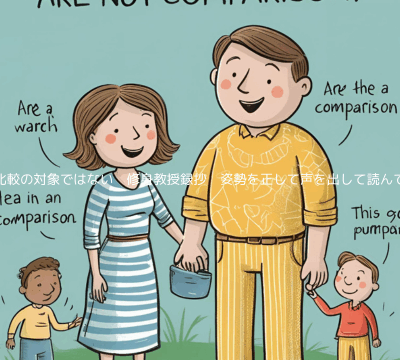真の読書
Release: 2022/10/22 Update: 2023/03/28
真の読書
真の読書というものは、自分の内心の已むにやまれぬよう要求から、ちょうど飢えたものが食を求め、渇した者が水を求めるようにであってこそ、初めてその書物の価値を十分に吸収することができる。【107】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
厳しいお言葉の章です。それは何故かというと読書の必要性がまざまざとわかりがっかり感があるからですね。
自分の担当のものがあるからあわてて本を読むという程度ではおめでたいというわけです。
外面的な義務や強制感に迫られて読んだ本は得るところが少ない。
それは先生のおっしゃる通りです。
学生時代をどう過ごしたか、その後もどう過ごしたかが悔やまれます。
本をのどが渇くがごとく欲して読むということの理解が難しいと感じていましたが、この修身教授録はそういうものに近いような気もしてきました。
もっと覚えておきたい限りなのです。
関連コンテンツ
大欲の立場にたつ 人間が真に欲を捨てるということは、実は自己を打ち越えた大欲の立場にたつということです。すなわち自分の一身の欲を満足させるのではなくて、天下の人々の欲を思いやり、できることなら、その人…
名・利というものは如何に虚しいものか。しかも人間はこの肉体の在するかぎり、その完全な根切りは不可能といってよい。 先生の数多い著述の中でも、めずらしい「隠者の幻」と題する小説風のものがあります。元東京…
その昔道元禅師が、求道のために遥ばる支那に渡って、ある禅寺に入れられた処、一人の年老いた長老の老僧が、炎天下に茸の筵の上に干しているのを見られて「この暑いのに、かような事をご自身でなさらなくても、誰…
そもそも物事というものは、すべて比較を止めたとき、絶対無上となるものであります。総じて善悪とか優劣などということは、みな比較から起こることでありまして、もし全然比較をしなかったとしたら、すべてがそのま…
優れた実践の背後には すべて優れた実践の背後には、必ずや常に一個の思想信念がある。【182】 #修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新 実践することの大切さは、何度…