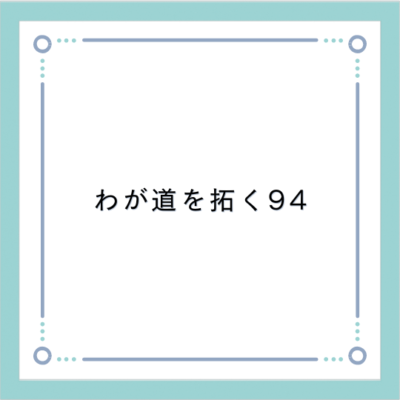置土産
Release: 2023/01/17 Update: 2023/01/17
置土産
今諸君らの生活が、真に深く、かつ内面的に大きかったならば、諸君らの精神は、必ずや後に来る人々のために、一種の置土産となることでしょう。さらにまた、私共のように教職にある者としては、その精神は、仮にその学校を去る時がありましても、もしその生活が真実であったならば、必ずや後に多少の余韻が残るようでなくてはなりますまい。【516】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
生きれば死に、来れば去る。
そのように循環しているわけですが平常すぐに忘れます。
実際、熱を出したりよか様々に体調を崩しても死ぬとは思っていないわけです。
現実を見ないようにしてしまうものです。
真実に生きるというのは、やり残しのない一日をいかに過ごそうとするかということかもしれません。
場を自分がもっているのに精一杯にならないのは問題が多い。
なんだか反省です。
関連コンテンツ
古来偉人は、すべて自分の置かれた境遇に於て立派に生きている。世間的な地位は天命ゆえ、それぞれの地位に安住して悠々とわが道を拓かねばならぬ。 運命を創る100の金言 偉人という人はどこかで何かを悟った人…
人間的威力を鍛錬する 真の修養とは、人間的威力を鍛錬することです。無力なお人よしになることは、大よそ天地隔たることと言ってよいのです。つまり真の内面的な自己を築くことです。その人の前では、おのずから襟…
教育者の使命 現世的欲望を遮断しつつ次代のために自己を捧げるところこそ、教育者の教育者たる真の使命はある。【282】 #修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新 修身…
人を知る われわれ凡人には、いかに優れた方でも、まず十年くらい私淑しないことには、その方の真のお偉さを知ることはできないようです。その人の真を知るとは、その方の現在わが国における位置を知るのみならず、…
道理を知る 人間は読書によって物事の道理を知らないと、真の力は出にくいものです。そもそも道理というものは、ひとりその事のみでなく、外の事柄にも通じるものです。【506】 #修身教授録一日一言 #森信三…