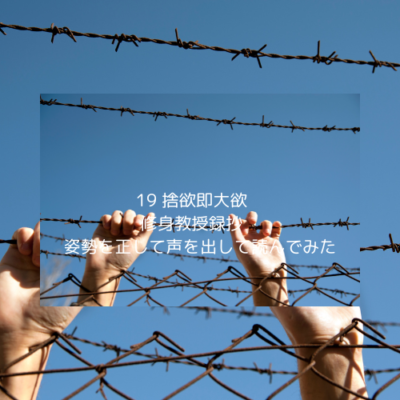読書① 66
Release: 2024/03/19 Update: 2024/03/19
肉体を養うためには毎日の食事が欠かせないように、心を豊かに養う滋養分としての読書は、われわれにとって欠くことのできないものなのであります。ですから人間も読書をしなくなったら、いつしか心の栄養不足をきたすと見て差し支えないでしょう。
運命を創る100の金言
読書の問題は何といっても実践項目に何かがなって日々の生活に生かしていけるのかという問題になると感じますね。
心に残る本を読んでいきたいものです。
ノウハウの書いてある本も実践しなければ意味は薄いものになりますし頭でかっちというのは先生の嫌うところですね。
本日の修身教授録はペスタロッチーの言葉なんですが、このペスタロッチーの本を2冊買ってみたのですがなかなか古い本で読めない本であります。こういう本は毎日一ページとかで読み進めるしかないのでしょうね。
積読してある本は結構難しくてとっつきにくい本が多いのですが、気合しかないでしょうね。強い意志が必要です。
最近は興味が分散して何を読んでいったらわからない状態ですが、何か本を読み返すのもいいかもしれませんね。
ごはんはしっかり食べているのに心の養分はかなり不足しているかもしれません。
様々に訪れることはある程度読書で解決できるかもしれませんね。
関連コンテンツ
単純なものだからこそ 植物というものは、動物、とくに人間から見れば、生命の最も低い発現段階といってよいでしょう。すなわち、宇宙の大生命は、植物としては、その最も単純な姿を示すわけです。が同時にまたすべ…
機械文明は止まるところを知らず、進歩し発達して、今やわれわれ人間は、しだいに機械によって圧迫せられ、さらに支配せられるようになってきました。このような事態を「人間疎外」という言葉で呼んでいますが、これ…
人間は、自ら積極的に欲を捨てるということは、意気地なしになるどころか、わが一身の欲を打ち越えて、天下を相手とする大欲に転ずることとも言えるのです。しかるに世間多くの人々は、欲を捨てるということを、単に…
この「即今着手」「迅速処理」の原則のほかに、期日の決まっている提出物の場合は、ゼッタイに期日を遅らせないことが大事です。そのためには、八十点カツカツの程度でよいから、とにかく期日までに仕上げることが肝…
われわれ人間は、いやしくも「生」この世にうけた以上は、それぞれの分に応じて一つの「心願」を抱き、それを最後のひと呼吸まで貫かねばならぬ。 森信三先生は、よく「内に心願を秘めて」とおっしゃいました。そし…