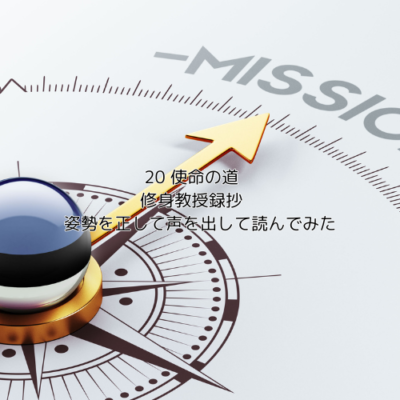優れた師②共に道を歩む
Release: 2022/09/03 Update: 2022/09/03
優れた師②共に道を歩む
優れた師匠というものは、常にその門弟の人々を、共に道を歩むものとして扱って、決して相手を見下すということをしないものであります。
ただ同じ道を、数歩遅れてくる者という考えが、その根本にあるだけです。ですから、自分一人が山の頂上に腰を下ろして、あとから登ってくる者たちを眼下に見下して、「何を一体ぐずぐずしているのか」というような態度ではないのです。【141】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
人生を多少なりとも変えてくれる人と出会う。
そういう縁を大事にするためには積極的にならなければなりませんね。
教授は、絶対的なタイミングで出会うべき人には必ず逢えるといいます。
自分の考え方は年によっても変わるし、読む本によって変わったり様々です。
今の自分の現状を多少なりとも変えていこうと力強く思うということもまた大切だと思います。
日々自分自身と葛藤している人がいい。
現状に満足している人はおもしろくないですね。
1日1mmの成長を目指していきたいものです。
関連コンテンツ
われわれ人間の価値は、その人がこの二度とない人生の意義をいかほどまで自覚するか、その自覚の深さに比例するといってよいでしょう。ところで、そのように人生の意義に目覚めて、自分の生涯の生を確立することこそ…
雑務は心がつくる 雑務という言葉は、私達のよく耳にする言葉ですが、「一言もってその人を知る」とは、まさにこのような場合にも当てはまるかと思うほどです。それというのも、その人自身それを雑務と思うが故に雑…
苦しい目に出遭ったら 人間苦しい目に出遭ったら自分をそういう目に遭わせた人を恨むよりも、自分のこれまでの歩みの誤っていたことに気がつかねばなりません。かくして初めて自分の道を開けるのです。また人間の内…
生命力の弱さがもたらすもの 人間が嘘をつくというのは、生命力が弱いからでしょう。勤勉でないというのも、生命力の弱さからです。また人を愛することができないというのも、結局は生命力の弱さからです。怒るとい…
自分の天分を発揮する② ではどうしたらよいかというように、それには、自分というものを越えた何物かに、自己をささげるという気持ちがなければ、できないことだと思うのです。【57】 #修身教授録一日一言 #…