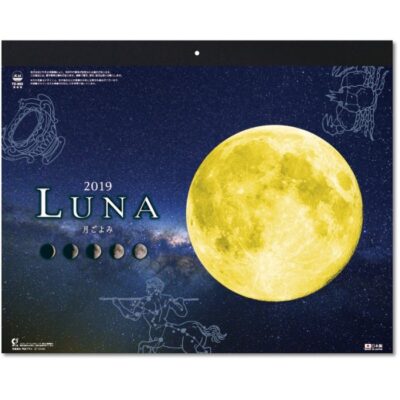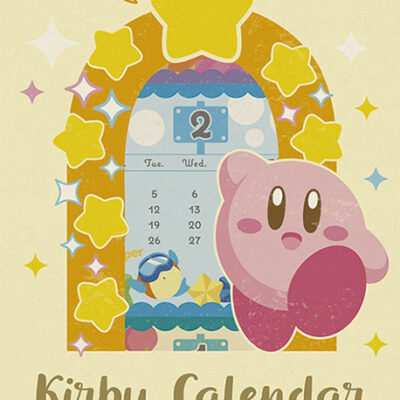三有礼|5月17日のことです。
Release: 2018/05/17 Update: 2018/05/17
三有礼
故ありて去るときは則ち君人をして之れを導きて彊を出でしめ、又其の往く所に先だたしむ。去りて三年返らずして、然る後に其の田里を収む。此れを之れ三有礼と謂ふ。(離婁下三章)
ゆえありてさるときはすなわちきみひとをしてこれをみちびきてさかいをいでしめ、またそのゆくところにさきだしたしむ。さりてさんねんかえらずして、しかるのちにそのでんりをおさむ。これをこれさんゆうれいという。(りろうしもさんしょう)
【訳】
何らかの理由で家臣が国を去らなければならなくなった時には、君主は使者に案内させて国境まで見送らせ、また、行く先々に使者を派遣して、(家臣の評価の高さを伝え、そこで)お仕えできるように計る。更に(その家臣)三年待っても帰らない時に、はじめてその家臣の土地や住居を没収する。このやり方を三有礼という。
孟子一日一言、5月17日、今日の言葉です。
部下がもしやめるという時、礼をつくすということが大事なんでしょうね。
徳というのはこのような積み重ねが大事なんだと思います。
たくさんの時間とお金をかけた人が去るというときは三有礼を思い出さねければいけませんね。
人それぞれいろいろな事情があるものです。
より良い人間関係が大事ですね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
本ある者 孟子曰く、「原泉混々として、昼夜を舎てず。科に盈ちて而る後に進み、四海に放る。本ある者は是れを之れ取れるのみ」(離婁下十八章) もうしいわく、「げんせんこんこんとして、ちゅうやをすてず。あな…
惻隠・羞悪・辞譲・是非の心① 惻隠の心は仁の端なり。羞悪の心は義の端なり。辞譲の心は礼の端なり。是非の心は智の端なり。人の是の四端あるや、猶ほ其の四端あるがごときなり。是の四端ありて自ら能はずと謂う者…
性を知れば則ち天を知る 其の心を尽す者は其の性を知るなり。其の性を知れば則ち天を知る。(尽心上首章) そのこころをつくすものはそのせいをしるなる。そのせいをしればすなわちてんをしる。(じんしんかみしゅ…
往く者は追はず、来る者は拒まず 夫子の科を設くるや、往く者は追はず、来る者は拒まず。苟も是の心を以て至らば斯れ之れ受けんのみ。(尽心下三十章) ふうしのかもうくるや、ゆものをおはず、くるものはこばまず…
人の不善を言はば 人の不善を言はば、当に後患を如何すべき。(離婁下九章) ひとのふぜんをいわば、まさにこうかんをいかんすべき。(りろうしもきゅうしょう) 【訳】 むやみに他者の不善を口にしていれば、必…