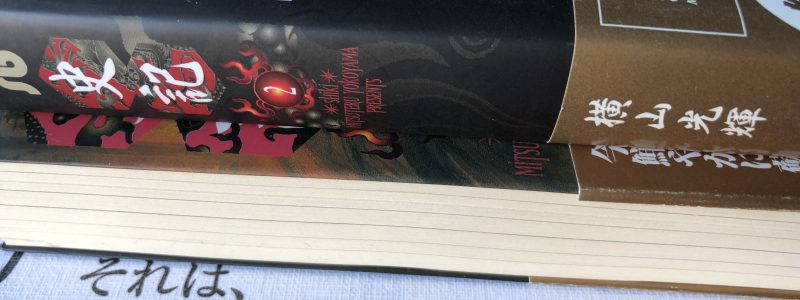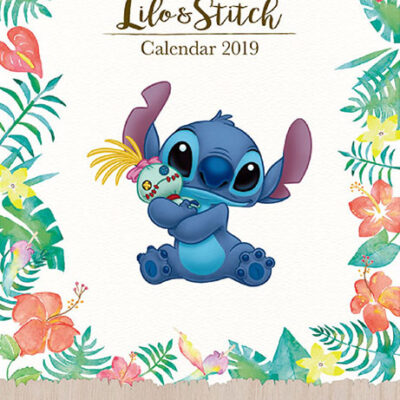半杓の水で|4月16日のことです。
Release: 2018/04/16 Update: 2018/04/16
半杓の水で
心すべきは水を粗末にせぬということです。
ある高僧は、ひしゃくに河水をくみ、半杓をもって朝の洗面をすまし、残りの半杓は、ていねいに川にもどしたと申します。
今、福井県永平寺に参拝致しますと、電車をすててしばらく上った谷川に、「半杓橋」という橋がかかっています。これがその聖なる遺跡だと聞きます。
丸山敏雄一日一話幸せになるための366話、4月16日のことです。
水は神聖なものという考えは大昔からあります。
それはきっと人間は水が無ければ生きてはいけないからでしょうね。
大切な自然の恵みだということをすぐに忘れてしまいます。
そして、半分くらいの気持ちで余裕をもつことも時として必要かもしれません。
行動いついても余裕を持つことが必要ですね。
今日一日朗らかに安らかに喜んで進んで働きます。
関連コンテンツ
生命の不滅というのことは、種において、族によって、祖孫を通じてはじめて不滅であって、祖先なき子孫はなく、子孫なくして生命の不滅なる理由がない。 宇宙の大生命は、不断の創造である、自在の生成である。何の…
動そのまま不動 万物万象ことごとく、常に変わりあらたまって、息(やす)む時がない。しかもそのまま、少しも「かわらぬ」。 「動」の側よりこれを見れば、常にやすみなく動いている。しかも、それが「不動」の側…
人間は、自分で自分の捕虜になっている。狭い柵の中にもぐりこんで自分勝手に苦しんでいる。おりというのは諸君の肉体である、さくというのは諸君の住宅である。肉体は心のいれもの(容器)ではないか。古人は言った…
我らは太陽民族 病気とは、気が病む事、心が当たり前でなくなっているのである。体が痛むという事は、心がいたんでいることである。心を清めれば、即座に体は清まる。明るい心が、身体を健康にし、家庭を明朗にし、…
洗面の意義 朝起きたら顔を洗うということは、だれでも知っている。けれども何の為に洗うのか。 洗面の意味は、まず全身を洗い清める、ということであります。 我が国では、到る所豊かな水に恵まれており、祖先た…