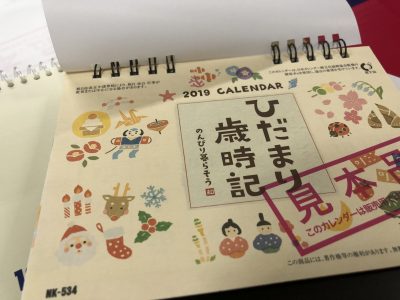涵育薫陶|5月21日のことです。
Release: 2018/05/21 Update: 2018/05/21
涵育薫陶
養とは涵育薫陶して其の自ら化するを俟つを謂ふなり。(離婁下七章)
ようとはかんいくくんとうしてそのみずからかするをまつをいうなり。(りろうしもななしょう)
【訳】
養うとは、仁の徳でうるおし育み、訓育教化し、自然に(よい方向)変わることを待つことである。
〇松陰は、この朱子の註の一部を取り上げ、「涵は綿を水でひたすという意味。育は幼児を乳で育てるという意味。薫はお香をたきこめるという意味。陶は土器を焼き固めるという意味である。人を養う場合も、この涵育薫陶のように行い、人々が自然に化せられて行くのを待つだけである」と記している。
5月21日の孟子一日一言の言葉です。
人材の育成はまさにこのような形でなければいけなんですね。
自然と感化されてよくなっていく。
社長、幹部、上司は徳のある人物にならなくてはいけません。
上から順にいけばきっと業績も上がるのでしょうね。
会社は理念で引っ張っていかなければならないと学ぶました。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
良能・良知 人の学ばずして能くする所のものは、その良能なり。慮らずして知る所のものは、其の良知なり。(尽心上十五章) ひとのまなばずしてよくするところのものは、そのりょうのうなり。おもんばからずしてし…
心を労する者は人を治め、力を労する者は人に治めらる。人を治めらるる者は人を食ひ、人を治むる者は人に食はる。天下の通義なり。(滕文公上四章) こころをろうするものはひとをおさめ、ちからをろうするものはひ…
禹は四海を以て壑と為す 禹は四海を以て壑と為す。今吾子は隣国を以て壑と為す。(告子下十一章) うはしかいをもってがくとなす。いまごしはりんごくをもってがくとなす。(こくししもじゅういっしょう) 【訳】…
君の臣を視ること手足の如ければ 君の真を視ること手足の如ければ、則ち臣の君を視ること腹心の如し。君の臣を視ること犬馬の如ければ、則ち臣の君を視ること国人の如し。(離婁下三章) きみのしんをみることてあ…
養ふ所以のものと知る 拱把の桐梓は人苟も之れを生(長)ぜんと欲すれば、皆之れを養ふ所以のものと知る。(告子上十三章) きょうはのどうしはひといやしくもこれをしょうぜんとほっすれば、みなこれをやしなうゆ…