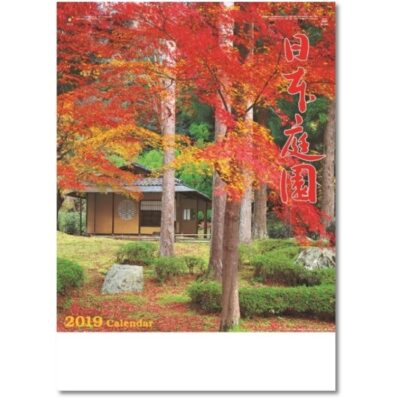賢者|1月6日のことです。
Release: 2019/01/06 Update: 2019/01/06
賢者
賢者にして而る後に此れを楽しむ。不賢者は此れありと雖も楽しまざるなり(梁恵王上二章)
けんじゃにしてしかるのちにこれをたのしむ。ふけんじゃはこれありといえどもたのしまざるなり。(りょうのけいおうかみだいにしょう)
【訳】
(民を思う)真の賢者であってこそ、(庭園内に飼われている鳥や動物などを)楽しむことができる。真の賢者でない者は、それらを心から楽しむことはできない。
〇松陰は、「文王は鳥や動物を楽しんでいるのではなく、民が楽しむのを楽しんでいる。これが、君臣上下が互いにその楽しむ、つまり、『偕(とも)に楽しむ』ということである」と記している。
1月6日、孟子一日一言の言葉です。
大きな心で大きな目で世の中を見ているのが賢者なのでしょうね。
やさしい眼差しを感じますね。
今の世の中は平均寿命が延びいろんなことに気づくのが遅くなっているような気がします。
吉田松陰で29歳、坂本龍馬で31歳、西郷さんで46歳。
どれだけ早くにいろいろなことに気づいたのでしょうね。
今ごろ論語や孟子に気づいているのは遅いですが気づかぬよりましかもしれませんね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
惻隠・羞悪・辞譲・是非の心② 凡そ我れに四端ある者は、皆拡めて之れを充たすことを知る。火の始めて燃え、泉の始めて達するが若し、苟も能く之れを充たさば、以て四海を保んずるに足り、苟も之れを充たさざれば、…
誉・毀 慮らざるの誉あり、全きを求むるの毀あり。(離婁上二十一章) おもんばからざるのほまれあり、まったきをもとむるのそしりあり。(りろうかみにじゅいちしょう) 【訳】 全く思いもよらないことで褒めら…
身に在り 人恒に言あり。皆天下国家と曰ふ。天下の本は国に在り、国の本は家に在り、家の本は身に在り。(離婁上五章) ひとつねにげんあり。みなてんかこっかという。てんかのもとはくににあり、くにのもとはいえ…
人に分つに財を以てする、之れを恵と謂ふ。(中略)天下の為に人を得る者は、之れを仁と謂ふ。是の故に天下を以て人を与ふるは易く、天下の為めに人を得るは難し。(滕文公上第四章) ひとにわかつにざいをもってす…
大夫は今の諸侯の罪人なり 故に今の大夫は今の諸侯の罪人なりと曰ふなり。(告子下七章) ゆえにいまのたいふはいまのしょこうのざいにんなりというなり。(こくししもななしょう) 【訳】 (今の大臣は皆主君の…