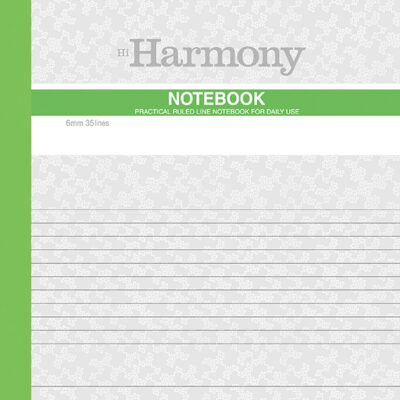耳という心の関門|9月5日のことです
Release: 2019/09/05 Update: 2019/09/05
耳という心の関門
聞えぬことを無理に聞こうとして、聞き耳を立てたり、また聞いても聞かぬふりをしたり、耳をとおしてわが心を偽ることは皆、耳の機能をにぶらせ、耳を聞えなくすることである。
「風疎竹に来る 風過ぎて竹に声を留めず雁寒潭をわたる 雁去って潭に影を留めず」。こういう明鏡止水の心の門戸、そこには関守はいない。出入自在の音の門戸、その道には、草一本、塵一つヲ止めぬ。たんたんとはき清められた真直な、みがき上げた道が通っておる。これが正しい心の奥堂に参ずる、耳という心の関門である。
9月5日、丸山敏雄一日一話幸せになるための366話、今日の言葉です。
耳というのはとても大切なものですね。
聞き耳を立てること、聞かないふりをすること、これは問題ですね。
耳からの情報を処理して自分で解釈しているのですからしっかりと聞くことは大切なことです。
コーチングでは傾聴、共感を言われます。
人の話しを聞くこと良い方向へ導くこと。
難しいことですね。
今日一日朗らかに安らかに喜んで進んで働きます。
関連コンテンツ
敬の心 敬はおのれ(己)をじっと見つめることから始まる。自分がここに生きているのは、日々食物をたべ、衣服を着、家に住むことができるからである。さらに、この生命は父母にうけ、祖先にうけ、ずっとさかのぼれ…
四囲の物質は、人を生かし、守り、正しい方向を示し、苦難を脱却せんと不断の努力をつづけている。 心朗らかに働いていれば万事は必ず好転する。 それで事情がどのように悪化しようと、商品が売れず、製品が推積し…
万物は元にもどる 宇宙はそのままで完全である。この全さを、いよいよ明らかにするため、欠け目ができる。しかし、欠け目は必ず元にかえる。 世は、歓楽の交響、光の映発でみちみちている。その喜びを真実にするた…
現在に生きる 人は常に、現在の一瞬に生きている。そのほかは我はなく、これを外しては人生はない。 過去はすぎさった現在であり。未来は来ようとする現在である。ただ今に生きる、これが人生である。 現在の一瞬…
仕事を追う 出発の良し悪しが、その日の仕事に、どのように関係するか。気をつけてためしてごらんなさい。仕事が順序よくいく。人が都合よく来る。話がよくまとまる。 それはなぜでしょうか。仕事を追うからです。…