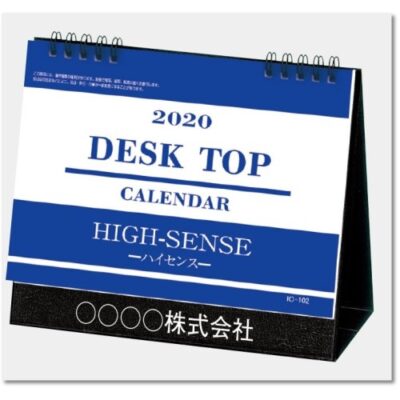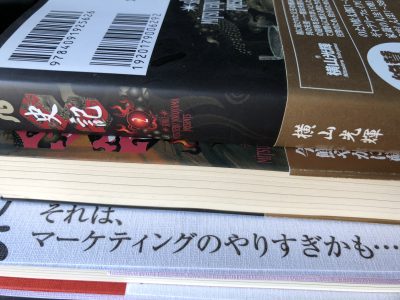男の意地|3月16日のことです。
Release: 2018/03/16 Update: 2018/03/16
仕事にかかる時は、帯を締め直さねばならぬ。太古の人たちは、野山で切り取ったかずらを腰に結び、平安朝時代のみやびおは石で飾りをつけた帯を束帯の上にしめた。
帯が地肌にしめられたものが「ふんどし」である。戦いの場合、重囲の中に陥って男の最後の心境を見せるときは、ふんどしをしっかりとしめ、白木綿を腹に巻き立てた。
商家の若者たちは、角帯をしめ、農村・漁村の青年は、六尺ふんどしをしめた。十五~十六歳に達すると「ふんどし取り」が行なわれ、これから一人前になった。
3月16日、丸山敏雄一日一話(幸せになるための366話)の言葉です。
帯を締め直すというのはこういうこういうことからきているんですね。
本日は、朝、除雪当番で更新できませんでした。
朝をしっかりと過ごすためには事前の準備も必要です。
いつなんどき何があるかわかりませんね。
しっかりと帯を締め直し新たな明日を迎えねばなりません。
明日一日朗らかに安らかに喜んで進んで働きます。
関連コンテンツ
チャンスは目の前に 生命を磨き、手入れ、これが教育であるのに、どこに目標がないというのか、生命の拡大と完成とが人の生活であるのに、どこにいったい不満があっておもしろくないのか、何に不明があってうちふさ…
貧乏画家、池大雅の家に来客がとまった。夜半、別室で紙がガチャガチャと鳴る音がする。 翌朝たずね聞くと、夫婦の休むフトンがないので画の用紙をかさねて、その中にもぐりこんでいたのである。 平賀源内にある時…
商品は天下の宝 あなたのお店に扱っておられる商品は、これこそ天下の宝です。 これを尊ぶことが、その商品を大切にするもとになるのですが、十分研究されておられますか。 研究することは、それに興味を持つこと…
正常心 動物は、本能によって、異常な働きをする。暗夜に物につき当らぬ。渡り鳥が、その方向を間違えぬ。 人は、そもそもそうした本心を持っているのであるが、我がままに堕して、そうした能力を失ってしまった。…
半杓の水で 心すべきは水を粗末にせぬということです。 ある高僧は、ひしゃくに河水をくみ、半杓をもって朝の洗面をすまし、残りの半杓は、ていねいに川にもどしたと申します。 今、福井県永平寺に参拝致しますと…