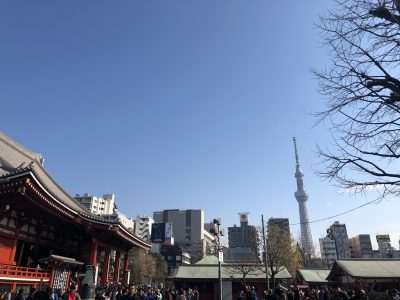主となる所・する所|7月7日のことです。
Release: 2018/07/07 Update: 2018/07/07
主となる所・する所
近臣を観るには其の主となる所を以てし、遠臣を観るには其の主とする所を以てす。(万章上八章)
きんしんをみるにはそのあるじとなるところをもってし、えんしんをみるにはそのあるじとするところをもってす。(ばんしょうかみはっしょう)
【訳】
朝廷に仕える近臣がどんな人物であるかは、彼を頼って身を寄せてくる人間を見れば分かる。また、遠方から仕官しにくる人がどんな人物かは、彼が頼って身を寄せる人間を見れば分かる。
〇松陰は、「心ある立派な人は徳によって集まり、つまらない人間は利益によって集まる」と記している。
7月7日、孟子一日一言の言葉です。
会社も交友関係もそういう点で見ることが大事なんでしょうね。
自分の交友関係を考えてしまいます。
何人の人がなにも聞かずにで付き合ってくれるのか。
きっと友達とか仲間を熱く語るような人間ほどだめなんでしょうね。
それもまた身から出た錆です。
今一度、徳について学びお役に立つ仕事をするしかないんでしょうね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
中国にして孟子に室を授け、弟子を養ふに万鐘を以てし、諸大夫国人をして皆矜式する所あらしめんと欲す。(公孫丑下十章) みやこのもなかにしてもうしにしつをさずけ、でしをやしなうにばんしょうをもってし、しょ…
堯の時に当りて② 舜、(中略)禹、九河を疏し、済・漯(の水)を瀹してこれを海の注ぎ、汝・漢を決し、淮・泗を排して之れを江に注ぐ。然る後に中国得て食ふべきなり。(滕文公上四章) しゅん、(中略)う、じゅ…
意を以て志を逆ふ 詩を説く者は、文を以て辞を害せず、辞を以て志を害せず、意を以て志を逆ふ。是れ之れを得たりと為す。(万章上四章) しをとくものは、ぶんをもってじをがいせず、じをもってこころざしをがいせ…
吏をして其の国を治めしめ 天子吏をして其の国を治めしめて、其の貢税を納れしむ。(万章上三章) 【訳】 天子の舜は別に役人を派遣して有庳国を治めさせ、租税を徴収させた。 【訳】 松陰は、朱子の註の一部を…
必ず規矩を以てす 羿の、人に射を教ふるには必ず彀に志す。学ぶ者も亦必ず彀に志す。大匠の人に教ふるには必ず規矩を以てす。学ぶ者も亦必ず規矩を以てす。(告子上第十九章) げいの、ひとにしゃをおしうるにはか…