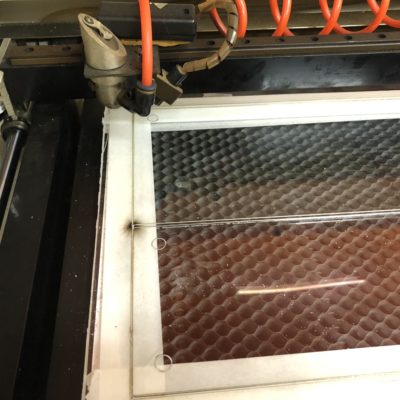大吏怒りて服せず、敵に遇えば懟(うら)みて自ら戦い、将は其の能を知らざるを崩と曰う。(地形)|5月30日
Release: 2020/05/31 Update: 2020/05/31
大吏怒りて服せず、敵に遇えば懟(うら)みて自ら戦い、将は其の能を知らざるを崩と曰う。(地形)
大吏怒而不服、遇敵懟而自戦、将不知其能曰崩。
「指揮官と他の将校の折合いが悪く、将校たちは指揮官に不満を抱いていて命にしたがわず、敵と遭遇すると勝手に戦い、指揮官も彼らの能力を認めていない状態を崩という」
”大吏”とは吏よりも上級の将校。大部隊の武将のこと。懟は恨む。ここでは高級将校たちが総指揮官を恨んでいるので、自分勝手に戦うことをいう。しかも、総指揮官は将校たちの才能を理解していない。こういう部隊はてんでんばらばらで、崩壊するのがおちである。
5月31日、孫子・呉子一日一話(兵法に学ぶ人と組織の動かし方365)の言葉です。
おはようござます。
こんな状態は完全に負けてします状態ですね。
これはやはり総指揮官に問題があるように感じます。
指導力不足な上に信用もしていない。
奢りなど問題なのでしょうか。
逆をいうと敵をこの状態にさせれば勝てるということです。
怖いことです。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
甲を巻きて趨(はし)り、日夜処(お)らず、道を倍して兼行し、百里にして利を争えば、(軍争) 巻甲而趨、日夜不処、倍道兼行、百里而争利、(則擒三將軍,勁者先,疲者後,其法十一而至。) 「たとえば、重い鎧…
善く戦う者は、これを勢いに求めて、人を責めず。故に能く人を択てて勢いに任ず。(兵勢) 故善戦者、求之於勢、不責於人、故能揮人面任勢。 「いくさ上手は、なによりも戦闘に勢いを求め、兵士一人一人の戦闘能力…
戦道必ず勝たば、主は戦う無かれと曰うとも、必ず戦いて可なり。(地形) 戦道必勝、主曰無戦、必勝可也。 「必ず勝つという見通しが立てば、たとえ主君が戦うなといっても、戦ってよい」これも前日の文章をふまえ…
疾(と)く戦えば則ち存(そん)し、疾く戦わざれば則ち亡ぶるものを、死地と為す。(九地) 疾戦則在、不疾戦則亡者、為死地。 「速やかに戦えば生存できる可能性はあるが、速やかに戦わなければ全滅する恐れがあ…
兵法は、一日に曰く度、二に曰く量、三に曰く数、四に曰く称、五に曰く勝。(軍形) 兵法、一日度、二日量、三日數、四日稱、五日勝。(地生度,度生量,量生数,数生称,称生勝。) 「兵法には次の五つの要素があ…