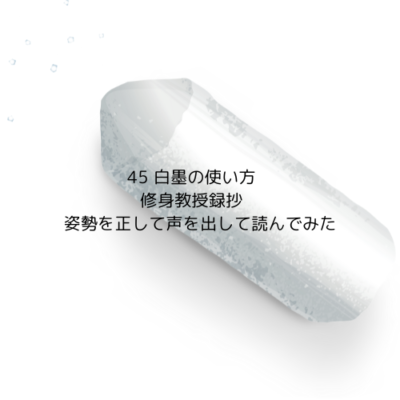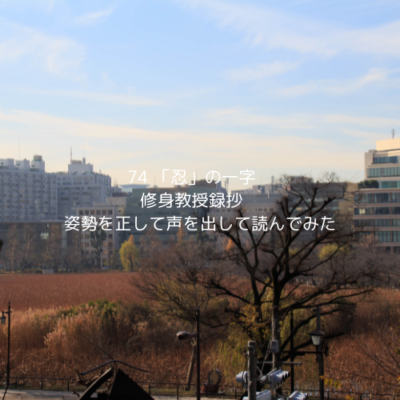本を読む
Release: 2022/05/09 Update: 2022/05/09
本を読む
本を読む場合、分からぬところはそれにこだわらずに読んでいくことです。そうしたところどころピカリピカリと光るところに出合ったら、何か印を付けておくのもよいでしょう。そして一回読み終えたら、少なくとも二、三か月は放っておいて、また読んで見ることです。そうして前に印を付けたところ以外にもまた、光るところを見つけたら、また新たに印を付けていく、そうして前に感じたことと、後に感じたことを比べてみるのは面白いものです。【137】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
たまに人間の言葉もここまで複雑怪奇に書ける人がいるのだと思うこともありますが、それでよいということでしょうね。
修身教授録もそのようなもので一日一言、少しづつでも理解したいと感じるからこそ購入するわけです。
古典的なものなど一気に読んでは見るものの理解しがたく、理解できない場合は眠くなるということがあります。
牛歩のあゆみです。
毎日のように少しづつ訓練です。
一章を毎日のように読み考えることで1mmの成長を期待したいところです。
耆に学べの清水克衛さんのところの感性で読むという部分を改めて思い出しました。
関連コンテンツ
苦労の用① 同一のものでも、苦労して得たのでないと、その物の真の値打は分からない。【134】 #修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新 そういうことは一応は肌感じて…
諸君、妙なことを申すようですが、諸君らは将来教壇に立ったら、白墨は太い方から使うがよいでしょう。これを唱えられた人が、私の知っている範囲で二人あります。その一人は泉北の考子、島田安治郎先生であり、今…
全力で迫る 尊敬するということは、ただ懐手眺めているということでなくて、自分の全力を挙げて相手の人に迫っていくことです。地べたをはってにじり寄っていくようにです。つまり息もつけないような精神の内面的緊…
忍耐ということはどういう意味があるかと申しますと、大体二つの方面があると思うのです。すなわち一つには、感情を露骨に現わさないようにする、とくに怒りの情を表さないように努めるという方面と、今一つは、苦…
時間の問題を解く ほんとうの真面目な生活、すなわち全力的な生活に入るには、どうしても時間を無駄にしないということが、何よりも大切な事柄になるわけです。しかしこの時間の問題も、結局はその人の根本の覚悟い…