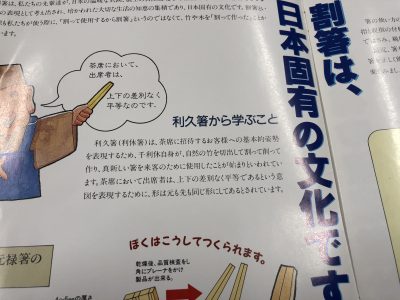養ふ所以のものと知る|8月26日のことです。
Release: 2018/08/26 Update: 2018/08/26
養ふ所以のものと知る
拱把の桐梓は人苟も之れを生(長)ぜんと欲すれば、皆之れを養ふ所以のものと知る。(告子上十三章)
きょうはのどうしはひといやしくもこれをしょうぜんとほっすれば、みなこれをやしなうゆえんのものとしる。(こくしかみじゅうさんしょう)
【訳】
(人間は)ほんの一握りか二握りくらいの小さな桐や梓の木でさえ、これを育てようと思えば、それを育てる方法を知っている。
〇松陰は、「『雞犬』(告子第十章)『無名の指』(同十二章)、そしてこの『供把の桐梓』の比喩は、人の心の迷いを破る上で有効である。俗人は目に見える顔などは飾るが、見えない心は放置してしまう。しかし、心ほど他者に知られるものはない。だから、心こそ最もおそろしく、頼もしいものである」と記している。
8月26日、孟子一日一言です。
種をまき、水をやる。
だれもが知ってることです。
心も同じで育てるべきものだし、育てなければいけない。
松陰先生の言うように実際話をしているだけで人に心は知られてしまいます。
顔やかっこうを心配する前に心を磨きましょうということですね。
今日も一日がんばります。
関連コンテンツ
斎戒沐浴すれば 西子も不潔を蒙らば、則ち皆鼻を掩ひて之れを過ぎん。悪人ありと雖も、斎戒沐浴すれば、則ち以て上帝を祀るべし。(離婁下二十五章) せいしもふけつをこうむらば、すなわちみなおおいてこれをすぎ…
其の身を潔くする 聖人の行は同じからざるなり。或は遠ざかり或は近づき、或は去らざるも、其の身を潔くするに帰するのみ。(万章上七章) せいじんのおこないはおなじからざるなり。あるいはとおざかりあるいはち…
理義の我が心悦ばすは 理義の我が心悦ばすは、猶ほ芻拳の我が口を悦ばすがごとし。(告子上七章) 【訳】 道理や徳義が万人を「本当にそうだ」と納得させ、満足させることは、牛や豚の美味しい肉が我々の舌を満足…
其の心に作れば其の事に害あり。其の事に作れば其の政に害あり。聖人復た起るも吾が言を易へじ。(とうぶんこうしもきゅうしょう) そのこころにおこればそのことにがいあり。そのことにおこればそのまつりごとにが…
志に食ましむるに非ず、功に食ましむるなり。(滕文公下四章) こころざしにはましむるにあらず、いさおしにはましむるなり。(とうぶんこうしもよんしょう) 【訳】 (報酬は)目的に対して与えるのではなく、成…