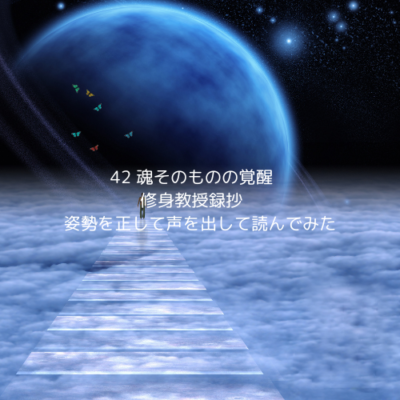言葉の深さ
Release: 2022/07/04 Update: 2022/07/04
言葉の深さ
お互いに常に耳慣れている言葉というものは、実は曲者であって、耳慣れた言葉が常に新鮮な響きをもってわが心に響くということは、よほど優れた人で、常に進んで息まない人でなければ、容易に至り得ない境遇と言ってもよいでしょう。ですからわれわれの多くは、このような境遇には至り得ないで、単に耳慣れ聞き古したこととして、深くは心にもとめないが、常だと言えましょう。したがってそこに新たなる響きを聞き、その深さに驚くことを忘れがちであります。【35】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
聞きなれる言葉というのもあるかもしれません。
常に唱和するような言葉もありますから、それは流れでなんとなくいつも通りというような場合もあるかもしれません。
いつも新鮮に響く言葉という言葉もあります。
となるといつでも気づき考える思考が常に進んで息まない人となるのかもしれません。
だらりと過ごしてはいけませんが季節的なものもあります。
熱中症には気をきつようと思います。
関連コンテンツ
自分の位置を知る われわれ人間は、一足飛びに二階へは上がれないように、結局は一つ一つ階段を登っていく外ないでしょう。そして最も大事な点は、現在自分の立っている段階は、全体の上から見て、おおよそ何段目く…
すべて一芸一能に身を入れるものは、その道に浸り切らねばならぬ。躰中の全細胞が、画なら画、短歌なら短歌にむかって、同一方向に整列するほどでいなければなるまい。つまりわが躰の一切が画に融け込み、歌と一体に…
置土産 今諸君らの生活が、真に深く、かつ内面的に大きかったならば、諸君らの精神は、必ずや後に来る人々のために、一種の置土産となることでしょう。さらにまた、私共のように教職にある者としては、その精神は、…
真の教育というものは、単に教科書を型通りに授けるだけにとどまらないで、すすんで相手の眠っている魂を揺り動かし、これを呼び覚ますところまで行かねばならぬのです。すなわち、それまではただぼんやりと過ごし…
「死」の徹見即「生」の充実。 「死」の絶望にボールを投げつけ、そのはねかえる力を根源的エネルギーとし、日々を真剣に生き抜くべし。 この言葉は、「人生二度なし」の内容をより具体的に象徴的に説かれたもので…