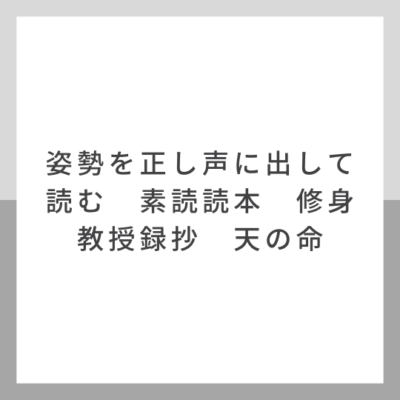言葉の深さ
Release: 2022/07/04 Update: 2022/07/04
言葉の深さ
お互いに常に耳慣れている言葉というものは、実は曲者であって、耳慣れた言葉が常に新鮮な響きをもってわが心に響くということは、よほど優れた人で、常に進んで息まない人でなければ、容易に至り得ない境遇と言ってもよいでしょう。ですからわれわれの多くは、このような境遇には至り得ないで、単に耳慣れ聞き古したこととして、深くは心にもとめないが、常だと言えましょう。したがってそこに新たなる響きを聞き、その深さに驚くことを忘れがちであります。【35】
#修身教授録一日一言 #森信三 #毎日投稿 #日常 #毎日ブログ #毎日更新
聞きなれる言葉というのもあるかもしれません。
常に唱和するような言葉もありますから、それは流れでなんとなくいつも通りというような場合もあるかもしれません。
いつも新鮮に響く言葉という言葉もあります。
となるといつでも気づき考える思考が常に進んで息まない人となるのかもしれません。
だらりと過ごしてはいけませんが季節的なものもあります。
熱中症には気をきつようと思います。
関連コンテンツ
われわれ人間というものは、すべて自分に対して必然的に与えられた事柄については、そこに好悪の感情を交えないで、素直にこれを受け入れるところに、心の根本態度が確立すると思うのであります。否、われわれは、か…
置土産 今諸君らの生活が、真に深く、かつ内面的に大きかったならば、諸君らの精神は、必ずや後に来る人々のために、一種の置土産となることでしょう。さらにまた、私共のように教職にある者としては、その精神は、…
すべての人間というものは、たとえ頭脳は大した人ではなくても、その人が真に自覚さえすれば、一個の天地を拓くことが出来るものです。だから人間は、世間的な約束事などには囚われないで、自分のしたいことは徹底的…
三味境を味わう われわれが真に、自己の充実を覚えるのは、自分の最も得意としている事柄に対して全我を没入して三昧の境にある時です。そしてそれは、必ずしも得意のことではなくとも、一事に没入すれば、そこにお…
生き甲斐 「生き甲斐のある人生の生き方」とはどういうのかと考えますと、結局それは、 (一)自分の天分をできるだけ十分に発揮し実現すること、 (二)今ひとつ、人のために尽くす という二か条で一応は十分と…